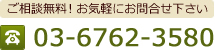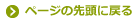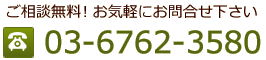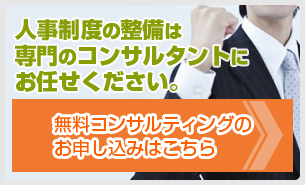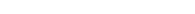株式会社マックブレイントップページ > 人事コンサルティングブログ
人事コンサルティングブログ
若手社員の早期戦力化について
2025年3月25日10:19 AM
各地で桜の開花が宣言され始め、今年も若い社員が入社してくる季節となりました。加速する少子高齢化による生産年齢人口の減少への対策として、若手の社員をいかに早期に戦力化できるかどうかが、全ての企業の課題となっています。
決して全てがそうとは言い切れませんが、これから入社してくる若者は、例えば徒競走で手を繋いでゴールするように一芸に秀でた子供よりも無難な子供に育つような教育を受けています。一方で、受験の偏差値により優劣が決められてしまう競争も経験しており、失敗が許されないというプレッシャーの中で育ってきています。また、日本の経済が停滞している時代背景に育った彼らは、「怒られることに慣れておらず、ストレス耐性が弱い」「リスクを避け、失敗しない無難な選択肢を選ぶ」「傷つきたくないという意識が強く、他人からの評価に敏感」というような特徴をもつ反面、「与えられた仕事は確実に行う」「自分の考え、意見をもっている」「情報収集が得意」「興味のあることは追及する」など、上司からすると物足りない面をもち合わせている一方で優れた面も多くもっています。
このような今の若手社員の特性を踏まえたうえで、企業は収益環境の厳しさが増す中で、一日も早く若手社員を戦力化し、収益に貢献してもらえるような人材に育てることが求められています。そのためには、若手社員育成の出発点として、彼らの成長を期待し、将来どのような人材に成長してほしいのかを上司がイメージし、そのイメージに基づいた育成の計画に沿ってキャリアアップさせていくことが必要です。そして、そうしたプロセスの中で、若手社員は上司や先輩からの日々の指導を通して自身の言動を振り返り、「基準行動とは何か」「自身の基準行動は他と何が違うのか」を考えられるようになり、結果、企業風土に沿った基準を身に付けていくことができます。
このように、積極的に上司が関わることで、本人のこれまでの価値基準や行動基準に改善点があるのであれば、いち早く脱却させ、企業人としてのマインドセットを図り、さらにそこで企業の基準を定着させることで「ルールやマナーを守る」「仕事の基本をわきまえている」社員として成長し、企業品格の向上や顧客からの信頼を得ることが可能となります。
早い段階から上司が若手社員との関わりを意識し、個々人の特性を理解して育成していかなければ、企業は成長どころか衰退してしまうリスクもありかねません。若手の社員であるからこそ、上司も指導しやすく早期の改善が期待できます。皆さんの職場では若手の育成は進められていますか。
カテゴリー:人材育成
社員の組織コミットメントについて
2025年2月25日4:46 PM
組織コミットメントとは、個人が所属する組織に対して抱く帰属意識やその概念であり、言い換えれば、社員に「自分はこの会社の一員である」という意識や感覚があり、「この会社で働き続けたい」という意欲がある状態のことを言います。こうした組織コミットメントを高めるためには、社員と会社がお互いに心理的な距離を縮めて、いかに信頼関係を構築することができるかがカギとなります。
組織コミットメントのメリットとしては、社員の仕事に対するモチベーションや集中力が上がることで、業務効率や生産性の向上が期待できることや当然、定着率が向上するので、組織にとって重要な人材の流出も防げるうえ、人材の採用コストを削減できることなどが挙げられますが、何より、社員と会社との信頼関係が強くなり、上司と部下、同僚や他部署とのコミュニケーションが活発となることで、メンバー同士に絆が生まれ、さらにコミットメントが高まるという良質なサイクルが構築されることにあります。
組織コミットメントを向上するための方法としては、まず、組織の存在意義とビジョンを共有することです。ここでのポイントは、全社員へ浸透するまでトップが理念やビジョンを発信し続けることであり、と同時に、1on1の機会等で会社の方向性について話し合うなどの方法も有効となります。但し、一方的な伝達ではなく、社員一人ひとりが自身の価値観や目標と照らし合わせながら共感できる対話の機会として設けることが重要です。
次に、人間関係構築の支援です。報連相や1on1、フィードバックの機会を活用してコミュニケーションの機会を意図的に設定し、上司と部下間での関係性の構築を図ると同時に、上司は部下の価値観や将来なりたいと思う姿を理解しようとし、組織の目標と重ね合わせながら支援することで、部下の成長を組織の成果の最大化につなげやすくなります。また、このようなコミュニケーションによって、社員一人ひとりの心身の状態の変化なども早期に気付いて対応できるため、離職率の低下などへの効果も期待できます。
最後に、職場環境を今一度見直して整えることです。全ての社員が完全に満足できる職場環境を構築することは難しい一方で、多くの社員に効果をもたらす施策とは何か、働きやすさとは何かを考え、環境を構築し続ける必要があり、実務面での改善や人事制度等の見直し、福利厚生の充実など、より良い職場環境の構築を進めることがポイントとなります。
このように、組織コミットメントがもたらす効果は、循環により相乗効果をもたらす良いスパイラルを構築することとなり、ひいては組織全体の成長に波及していきます。皆さんの職場の組織コミットメントはいかがでしょうか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
社員一人ひとりのリーダーシップの必要性について
2025年1月28日11:37 AM
所謂、「強い組織」「挑戦できる組織」を作っていくためには、リーダーシップの総量を増やしていくことが求められます。一方で、「リーダーだけでなく、サポート役の社員も組織には必要なのではないか」、或いは「リーダータイプとサポータータイプの社員がそれぞれの強みを活かすことでいいのではないか」というお考えの経営者の皆さんも少なくないと思います。
リーダーシップとは、「メンバーに働きかけることで巻き込んで動かす影響力」という「能力」であり、「役割」であるマネジメントとは種類が異なるため、実は誰もが発揮できる可能性を秘めています。一方で、リーダーシップが誰でも発揮し得るものにもかかわらず、マネージャーやリーダーだけが発揮するものと思われているのは、リーダーシップが権限行使と混同されていることがあるのかもしれません。権限行使とは、管理職などの役職者としての立場に与えられた部下の意向に関係なく一方的に命じることができる権限を行使することであり、能力として発揮するリーダーシップとは性質が異なります。
リーダーシップを発揮できる社員が、良きサポーターの役割も果たすことができることと同じように、良きサポーターであるメンバーも、リーダーとなれるポテンシャルを備えている可能性は十分あり、さらに言えば、どのような立場であれ、場面や状況に応じてリーダーシップを発揮することは必要であり、立場で線引きしてしまうことは、折角のメンバーの成長や能力の開発の機会を奪ってもしまいかねません。
技術の進化をはじめとした加速度的な環境変化の時代である現在、共通認識の方向性を踏まえたうえで、メンバー一人ひとりが自律的に行動する「現場力」が問われています。「現場力」とは、現場という集合体がもつ能力、知識、技術、姿勢、意識などの総称であり、それぞれのメンバーが単独で動くのではなく、お互いに影響しあったり、周りを巻き込んで連携しながら仕事をすることで、より一層チームの成果は高まります。
上司が部下のリーダーであり、部下が上司のサポーターであるように、上司であっても、時として部下の最良のサポーターとなる必要があり、メンバー同士であっても、状況に応じてリーダーとなり、サポーターとなることが求められます。このような「誰もがリーダー、誰もがサポーター」という柔軟で流動的なチーム作りを目指すことによって、リーダーシップキャパシティが最大化された「強い組織」「挑戦できる組織」が現実化するのではないでしょうか。皆さんは、どうお考えになられますか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
人材育成の取り組みを戦略的に行えていますか
2024年12月27日12:29 PM
早いもので今年も年の瀬を迎える時期となりました。今年も多くの研修を打たせていただく機会を頂戴しましたが、そうした中で思うことは、企業によっては、果たして戦略的に人材育成を行うことができているのか、ということです。
人材育成とは、企業が成長するために社員の人としての成長やスキルアップを促すことであり、その目的が「企業の成長」に置かれているため、ただ単に社員の成長やスキルアップを目指すのではなく、企業のビジョンやミッションへの共感と、さらにそれを踏まえて貢献できる人材を育成することとなります。
一方で、人材育成はすぐに結果に繋がるものではなく、長期的な視点が必要であり、単発的な研修や奨励された資格試験を受けさせるといったことだけでは不十分であり、組織の業績に貢献できるような人材を育成していくためには、企業文化や経営方針、人事戦略を踏まえて計画的に管理しながら育成していくことが必要です。そこで、戦略的に人材育成を行っていくためには、以下の3つの視点から現行の教育体系を見直していく必要があります。
まず、「人事戦略と教育体系が一致しているかどうか」です。教育と言っても、学問ではなく業績向上に貢献できる人材を育成~輩出することが重要となるため、経営方針や事業戦略、人事戦略、教育体系とは一本の命脈で繋がっている必要があります。OJTやOFF-JT、SD(自己啓発)等の社内の育成サイクルにおける成果が、業績を向上させる人材の輩出に直結していることが最大のポイントとなります。
次に、「保有すべき能力要件が明確に言語化されているか」です。育成の目標を抽象的なままにせず、具体的な形として明確化することが肝要であり、求められる役割と担う職務、それを達成するための成果行動を体系的に言語化することで、実務能力と業績の向上をリンクさせることができます。そのため、人材要件を明確にして目標を設定し、その目標に対する現状を把握しながら、必要な指導・教育を行っていくことが求められます。このように目標が明確になることで初めて、効果的な能力開発が実現し、業績向上へ貢献できる人材の育成に繋がり、ひいては組織力の強化に波及していきます。
最後に、「長期の視座に立って計画的に行われているか」です。人材育成の観点からみれば、OFF-JTは能力開発の一手段に過ぎず、いくら印象に残る研修を実施したとしても、その記憶は忘却曲線に沿って失われていってしまいます。そのため、効果的な人材育成を行う重要なポイントは、OJT・OFF-JT・SDをいかに段階的かつ計画的に配置し、それぞれを有機的に連携させながら育成サイクルの定着を図っていくかにあり、さらに社員一人ひとりの実務における成果行動の実践度を観察~評価することで、目標に対する現状を正確に把握し、それを育成サイクルに柔軟に反映していくことが求められます。
人材育成というとOJTやOFF-JTを思い浮かべる方が多いかも知れませんが、人材育成の手法は多岐にわたって様々なものが存在します。一方で、人材育成が戦略的ではなく場当たり的であったり、組織の方針や戦略とブレがあれば、どんな方法で行っても却って逆効果にもなりかねません。人材育成はいかに戦略的に計画的に行えているかが重要です。皆さんの職場では、どのように行われていますか。
カテゴリー:人材育成
チームを適切に機能させるタスク管理について
2024年11月30日10:48 AM
これまでも、マネージャーやリーダーがチームを管理することの重要性は指摘されてきましたが、個々人の価値観や働き方が多様化している昨今、チームを完全にまとめ上げることはとても困難になりつつあり、チームメンバーがバラバラと働いている状態で、「一人ひとりのタスク量や進捗状況をどうやって管理するか」「どうすれば、個人プレーではなくチームワークを高められるか」など、チームマネジメントに悩む上司の皆さんは少なくないのではないでしょうか。
一方で、直訳すると管理となるため、マネジメントとは単にメンバーを管理統率することと理解しているビジネスパーソンは少なくなく、例えば、マネージャーがメンバーに対して逐一指示を与えて進めているだけでは、チームの生産性が高まる域までに至ることはまずないと言ってもいいいでしょう。
このような上司の皆さんの悩みの多くは「タスク管理」に端を発しています。そこで重要となるのが、プロジェクト管理とタスク管理の違いを知っておくことです。プロジェクト管理とはプロジェクト全体の進捗やスケジュールを管理し、プロジェクトを円滑に進めていくことであり、それに対し、タスク管理とは大きな仕事を小さな仕事に分解し、個々のタスクの優先順位付けを行うことを指します。
チームを適切に機能させるためには、プロジェクト管理だけでは不十分であり、プロジェクトの成功には、個々のタスクの積み重ねが影響するため、マネージャーは、従来のプロジェクト管理に加えてタスク管理も行う必要があります。「タスクの抜け漏れはないか」「業務が止まってしまっているチームメンバーはいないか」「タスクの分量や割り振りは適切か」など、チーム全体のタスクをチェックしていくことが、結果的にプロジェクト全体の成功に繋がります。
そのためには、それぞれのメンバーが抱えるタスクを見える化し、マネージャーも含めた全員がプロセスやタスクの進捗状況を把握できる仕組みを作ることが必要です。タスクの納期や進捗状況を全員で共有できれば、タスクの抜け漏れを防止し、プロジェクトを計画通りに進めることができ、メンバー一人ひとりが他のメンバーの状況を考えながら行動できるので、チーム内の仕事のパス回しがスムーズになり、お互いを助け合いながら進めていくことが可能となります。
さらに、マネージャーがメンバー一人ひとりのタスクをチェックし、「特定のメンバーに業務量が偏っているような事態になっていないか」「タスクの処理時間が長く、ボトルネックになっているプロセスはないか」などを分析し、全員のタスクの見える化をより鮮明にしていくことで、メンバー同士でサポート、フォローできる体制が強化され、チームとしての組織力が向上されます。また、タスク毎に手順や作業方法を一枚のカードに記載した「タスクカード」を作成して活用することなどでも、業務の進め方が共有され、業務プロセスの標準化に非常に有効な仕組みとなります。
組織力を高め、チームを機能させるための第一歩が「タスク管理」です。皆さんのチームはいかかでしょうか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
ビジネスで重要視される目標設定について
2024年10月25日11:27 AM
目標設定とは、「目的」を達成するための行動や方針、施策を設定することであり、最終的なゴールへ向かうまでに必要な複数の要素として欠かせないものです。目標設定がビジネスで重要な理由は、進むべき方向性を明確にし、時間やコスト、労力を最小限に抑えて最短ルートで目的を達成するためです。目標の達成に必要な時間やコストの把握、リソースの適切な把握や管理に役立つ一方で、適切な目標設定ができなければ、最終的なゴールが達成されないだけでなく、達成のためにやらなければならないことを洗い出せなくなってしまうことになります。
「目的」と「目標」の違いは、「目的」は、最終的に成し遂げようとする事柄や全ての行動を方向づける根拠となるものであり、ビジネスて例えるなら、企業全体で達成したい「最終的な目標」と言えます。これに対し、「目標」は、目的を叶えるために段階的に設ける指標であり、目的を目指すプロセス上での一定期間における到達地点のようなものです。複数の目標を段階的に達成していくことで目的に近づいていくという目的を追求するための手段であり、必ず目的をベースに設定しなければなりません。
目標には発生型と設定型の二つのタイプが存在します。まず発生型は、既に発生してしまっている物事に対して設定される目標です。既存のあるべき姿と現状のギャップから発生する目標のため、誰でも理解しやすく共有も容易に行うことができます。発生型目標の設定の考え方としては、「過去⇒事実⇒問題の解決」というイメージです。一方の設定型は、自らの意志で自発的に設定する目標であり、思い描く新しいあるべき姿の提案のため、なぜその目標にしたのかを明確に言語化し、周囲を納得させるだけの根拠の説明が必要となります。考え方としては、「未来⇒意志⇒新しい価値」というイメージです。
目標の設定のプロセスについては、アメリカの学者ジョージ・ドランが提唱したゴール設定のフレームワークであるSMARTの法則が役立ちます。
- S=Specific(具体的な):定性的な内容ではなく、数値化した定量的な内容であるか
- M=Measurable(測定可能な):達成度合いが測定できる内容か
- A=Achievable(達成可能な):努力すれば達成できる現実的な内容か
- R=Relevant(関連性のある):企業のミッションや自分のなりたい姿などゴールと関連性のある内容か
- T=Time-bound(期限のある):いつまでにどの状態を目指すか
ポイントは、ぼんやりではなく誰にでもわかるように表現すること、進行や達成の度合いを定量化して表現すること、希望や願望ではなく現実的で達成可能な内容を設定すること、組織の方針から外れない目標を設定すること、必ず明確な期限を設定すること、の五つになります。こうしたSMARTの法則に沿って考えていくことで、具体的で進捗管理しやすく、メンバーのモチベーションを維持できる「目的」をベースとした「目標」の設定が可能となります。皆さんのチームの目標はどのようなものですか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感,目標管理
コンフリクトマネジメントについて
2024年9月26日12:23 PM
異なる価値観や年齢、性別をもつ個人の集まりである企業組織においては、その大小にかかわらず様々な対立や衝突を避けては通れず、現場では日々、個々に顕在的または潜在的な葛藤や不満が生まれています。そうした個々が思い描く葛藤や不満はネガティブなイメージとして捉えられがちである一方で、見方を変えれば、異なる意見や見解として組織の活性化や新しいアイディアとして変換できるかもしれない可能性ももっています。
「コンフリクトマネジメント」とは、そうした組織内で生じる衝突や対立を戦略的に活用して、組織の変革や強化に役立てようとする手法であり、コンフリクトを上手にマネジメントすることができれば、チーム内での質の高い議論やメンバー同士の相互理解といったメリットを生み出すことも可能となります。そのため、職場環境や人間関係を改善し、さらにチームやメンバーの成長に繋げることができるように、破壊的な対立ではなく、いかに建設的な対立に変えていくことができるかがカギとなります。
職場におけるコンフリクトは、①仕事に関する目標や問題についての意見やアイディアの衝突によるタスクコンフリクト、②仕事への価値観や取り組み方、進め方についての考え方の相違によるプロセスコンフリクト、③パーソナルな人間関係から生じる感情の対立によるリレーションコンフリクトの3つの種類に分類されます。①と②についてはマネジメント次第でチームの活性化に繋がる生産的なコンフリクトととも捉えることができますが、③については放置してしまうと、メンバー間に不安や緊張をもたらす非生産的なコンフリクトであり、「嫌い」「腹が立つ」など感情的にもつれてしまえば収拾がつかず解決が困難になることも少なくなく、対処が遅くなればなるほどチーム内のストレスや不安感は大きくなってしまいます。
こうしたコンフリクトが発生した際に、メンバーがどのような態度をとり、それに対してどのような反応が見られるかは大きく分けて次の5種類に分類されます。
| 態 度 | 反 応 | |
| 強制 | 自分の意見を一方的に相手に押し付ける | 押し付けられた相手は不公平感や不満を抱きやすい |
| 妥協 | 双方が妥協し合って、落としどころを探る | 問題の解決はできるが、中途半端な結論になりがちで、成果の満足度は低い |
| 受容 | 相手の意見を優先して受け入れる | 一方が自身の意見や主張を抑え込むため、Win-Loseの関係性になってしまう |
| 回避 | コンフリクトそのものを避ける | 対立は起きないが、問題は回避されるので、先送りになってしまう |
| 協調 | 互いの意見を尊重し合い、建設的な議論で解決を目指す | Win-Winになる可能性が高く、新しいアイディア創出のチャンスにも繋がる |
「強制」については強い上司やリーダーが恒常的に行いがちであり、「妥協」については日常的な解決策である一方で習慣化しないように注意する必要があります。「受容」と「回避」についてはリレーションコンフリクトにおいて放置されがちです。言わずもがな、コンフリクトマネジメントの目指すべきゴールは「協調」となるわけですが、一方で、先の4つの状態で落着せざるを得ないケースは少なくありません。そのため、上司である自分やメンバーがどのような態度や反応をとっているかを冷静に把握し、客観的に判断することで、その状況に応じた適切なマネジメントを行うことが求められます。このような際、皆さんはどのようなマネジメントを行われていますか。
カテゴリー:人材育成
チーム機能を高めるエンパワーメントについて
2024年8月27日11:38 AM
エンパワーメントとは、上司がメンバーに実行プロセスにおける意思決定の権限と責任を付与することで、メンバーに主体的かつ自律的な行動を促していくことであり、ビジネスシーンだけでなく、医療や福祉、教育、社会活動など、幅広い分野で重要視されています。ビジネスにおいては、所謂タレントマネジメントの手法の一つとして、チームに所属するメンバーの能力や経験を情報として管理し、人と仕事との適切なマッチングを図ることと捉える側面もあります。
一方で、一定レベルのスキルを有するメンバーに対しての人材育成マネジメントであり、どんなメンバーにでも機能するわけではなく、例えば、新人や若手にミスが許されないような重要な仕事や非常に緊急性が高い仕事を任せてしまえば、無責任なアサインとなってしまうため、対象となるメンバーの意欲や力量、状況を把握して、本人が努力することで、現実的に達成を見込むことができるエンパワーメントの実行が望まれます。
エンパワーメントが重要視されている理由としては、まず、スピーディな意思決定が挙げられます。従来のマネジメントは、指示命令する側と命令を受け取る側が明確に分かれており、権限と責任は指示命令する側に集中している命令管理型が主流でした。一方で、ビジネスを取り巻く環境の変化が激しく、スピーディな意思決定とアクションが求められるようになってきている昨今、経営者やマネージャーが全ての案件や問題などに主体的に関わることは難しくなってきています。さらに変化していくビジネス環境に対応するために、迅速かつ柔軟な判断が求められる局面では、上司に状況を説明して指示を仰いでいる過程でタイムラグが発生してしまいます。そうした中、メンバーに権限を渡し、現場で対応してもらうというエンパワーメントの実行が企業としての競争力やチームとしての機能性をより高めるという観点から注目されています。
次に、顧客満足度の向上です。現場のメンバーに意思決定の権限を付与することで、顧客満足度が向上するケースも期待できます。例えば、クレームやトラブルが発生した際に、直接接点のあるメンバーが権限をもっていれば、現場でスピーディに状況判断し、解決策を選択して対応することができます。このように、裁量権をメンバーに移管して簡素化することにより、意思決定が迅速化されるだけでなく、現場での対応力が高まり、よりニーズに密着した柔軟性のある意思決定が可能となります。
さらに、主体的に行動するメンバーが増えることも、エンパワーメントが重要視される理由の一つです。上司が全ての意志決定をしていれば、そのうち部下は思考停止し、「上司の判断を仰いで作業をする」という受け身のスタイルが出来上がってしまいます。そのため、エンパワーメントによって、自分の責任として自分で考え、主体的に行動できる社員を増やしていくことが求められます。これまで上司が行っていた判断を自ら判断し実行するという経験を積むことにより、判断基準や判断のタイミングを学びながら業務遂行能力が高まることで、メンバーに主体性や自律性が育まれていきます。
そして最後に、上司がより重要な案件にフォーカスできることが挙げられます。部下のあらゆる業務のチェックや意志決定を行っていれば、それだけで上司の時間は削られてしまいます。そのため、部下への権限委譲によって組織にとって大事なリソースである上司の時間を確保することで、本来のマネジメントや高度な仕事、より経営に近い案件に注力して取り組むことができるようになります。
今回はエンパワーメントが重要視される理由についてご紹介しました。皆さんの職場では、効果的なエンパワーメントが実行されていますか。
カテゴリー:人材育成
職場リーダーに求められる情況把握力について
2024年7月26日10:46 AM
「情況把握力」とは、2006年に経済産業省が職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力として提唱した社会人基礎力の12の要素の中の1つであり、「自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力」と定義されています。
組織やチームの活動において、計画通りに進むことは稀であり、目標に向かって進むプロセスで問題やトラブルが発生した際、リーダー自身やメンバーの「情況」を把握し、それぞれがとるべき具体的な行動の理解と共有が求められます。「情況」とは、物事のその時々の在り様のことであり、様々な事象や人々の仕事、感情などを客観的かつ論理的に理解すると同時にポジティブな面もネガティブな面も把握し、問題点やリスクを事前に察知するための「情況把握力」は、職場リーダーにとって非常に重要なスキルと言えます。一方で、情況把握力を単に「状況」を把握する能力と理解しているビジネスパーソンは少なくありません。
「情況把握」と似た言葉に「状況把握」という言葉があり、読み方は同じですが、それぞれには意味の違いがあります。「情況把握」が、自分自身を理解することは勿論、周囲のメンバーの内面や関係性にも思量を及ばせることであることに対して、「状況把握」は、自分自身やその立場、環境などの情報を収集し理解することであり、自分とメンバーの内面や関係性にまで焦点を当てておらず、主体的に行動することも限定されていません。そのため、いくら「状況把握」が優れていたとしても、必ずしもチーム内が活性化、機能化する保証がない点が「情況把握」との大きな違いとなります。
「情況把握力」を構成する3つの要素の一つ目は、言わずもがな、自分や相手が置かれている状況を把握し、物事との関係性を理解することであり、当然、状況の変化に気付くことやリスクを想定することも含まれます。さらに、一から十までの全てについての情報を収集することが出来なくても、推測し本質を見抜くことを起点にして自分で考え、全体像を捉えていくことも求められます。こうした意味で考えると「空気を読む力」とも言えるのかも知れません。
二つ目は、優先順位をつけて、すべきことを考えることです。例えば、店長から商品棚の整理をするよう指示されたタイミングで、急にレジ前に多くの来店者が並び始めてしまったとします。ここで優先されるべきは来店者へのレジ対応であり、優先順位は、まず「レジ対応」、次に「商品棚の整理」となります。極めてシンプルな例ではありますが、仕事では複数の物事を同時に進めなければならない場面もあるため、変化し続ける状況に対して、正しい優先順位を選択し実行していくことが求められます。
三つ目は、先を見通し行動に移すことです。組織が利益を生み出し続けるには、現状を把握し、この先に起こる変化に常に対応していかなければなりません。例えば、新しい工事計画を実行する際、全くトラブルがなく計画通りに進むとは限らず、どこかで不具合が生じたり、クレーム等が発生するケースも考えられます。そのため、トラブル等が起きた時でも対応できるよう、様々なパターンを考えておくことがとても大事な段取りとなります。さらに、「情況把握力」が高いビジネスパーソンであれば、冷静に状況を把握して最悪の場合も想定しながら行動できるため、将来的に経営やマネジメントにかかわるポジションなども期待される存在ともなり得ることができます。皆さんの職場のリーダーの「情況把握力」はいかがですか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
ビジネスパーソンに求められる計画力について
2024年6月25日11:09 AM
組織には目指すべき目的を実現するために、経営計画、事業計画、チームや個人の計画など、多くの計画が存在し、組織の中で仕事をするためには、周囲の人たちとの協力は欠かせません。そのため、そうした周囲の人たちに納得して仕事してもらうためにも、期限までに実行完了するために必要な目標やタスク、リソースなどを明確にし、タイムラインを設定した計画が必要不可欠と言えます。
一方で、計画を立てることができれば仕事が進むというわけではなく、計画には想定外の事態やトラブル等の発生が憑きものであり、そうしたトラブルを想定していなければ、対策が遅れるばかりでなく、さらなるトラブルを誘発し、問題を拡大させてしまうリスクも生じかねません。そのため、ただ計画を立案するだけでは不十分であり、実行可能な計画であることや状況に応じて修正できることがとても大事なこととなります。
そこで求められるのが計画力です。計画力とは、2006年に経済産業省が提唱した「社会人基礎力」の1つであり、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つで構成されており、計画力は、「考え抜く力」の一要素として位置づけられています。
ビジネスパーソンに計画力が必要な理由の一つ目は、どんな業務にも時間的制約があることにあります。顧客からの信頼を保つためにも、納期の遅れは許されず、当然ながら、工程やタスクごとに進捗を守ることが求められます。一方で、計画力が低ければ、工程数の見積もりや時間配分に無理が生じ、納期の遅れを引き起こしかねなません。そのため、あらゆるタスクを列挙し、それらに優先順位をつけ、適切に時間を見積もる計画力はビジネスパーソンにとってとても大事なスキルの一つと言えます。
二つ目は、言わずもがな、スケジュールの調整です。時間的制約があるからこそ、スケジュールの調整が必要であり、元々の計画に対して、遅延がどの程度の影響があるか、どのタイミングで調整すべきかを判断しなければなりません。さらに、業務には不確実性があり、外部環境の影響に左右されるため、長期的な計画ほど、計画通りに進まないことは珍しいことではなく、計画力が高ければ、想定外の事態にも複数の次善策を見出すことができます。
三つ目は、業務の効率化です。タスクに充てられるリソースには限りがあるため、効率的な手順や方法でスケジュールを進める必要があります。計画力が高ければ、優先順位を明らかにすることができ、必要のない作業に時間を割いて未完了のタスクが増えるということも回避できます。そのため、メンバーの抱える負担が軽減され、業務の質を落とすことなく、業務を効率化させることが可能となります。
このように、計画力はビジネスパーソンにとって必要不可欠なスキルと言っても過言ではないと思います。皆さんの職場はいかがですか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
チームの成果に効果的なOJTについて
2024年5月28日11:07 AM
皆さんの職場では効果的なOJTが行われていますでしょうか。OJTは職場で実務をさせることで行う従業員への職業教育のことですが、OJTをただ単に「仕事を教えること」と理解している上司の皆さんは少なくないのではないでしょうか。
人は組織の重要な経営資源であり、人が育つことほど組織にとって心強いことはありません。一方で、経営者から見た事業運営の目的は、利益の創出、事業の発展、社会貢献、社員の生活水準の向上など様々ですが、つまるところ社員に求めるのは「成果」であり、その実現のための方法の一つが社員一人ひとりの能力向上であり、そうした社員の能力をチーム機能に反映し「成果」に結びつけるためにOJT という手法をとっているに過ぎず、社員が育つことが組織の最終的な目標ではありません。したがって、「仕事を教えること」がOJTの一貫であることは間違いありませんが、実際にはもっと範囲が広く、「OJT=能力開発+成果」と捉えることが上司の皆さんには求められます。
さらに、OJTを行う上司は部下に対しての「思い込み」を止めることが必要です。まず、同じ「経験」をしているという思い込みです。時代が変わり、若い社員は上司の皆さんが育った時代と全く違う経験をしていることも多く、「これくらい言わなくてもわかるだろう」という考えは通じなくなってきています。そのため、ルールを共有したり、コミュニケーションをしっかり取ったりすることで、互いの認識にズレがないかを確認する必要があります。さらに、指導の際にも抽象的な伝え方ではなく、できるだけ具体的に伝えることが求められます。特にコロナ禍の学生時代を経て入社してきた若い社員は、これまで以上に経験不足、情報不足の部分を汲み取った接し方を心がける必要があるように思います。
次に、同じ「価値観」を持っているという思い込みです。価値観も多様化しているため、上司のモチベーションの源が部下と同じだとは限りません。そのため、それぞれの社員のモチベーションの源はどこにあるのか、何を大切にしたいと思っているのかを考えながらマネジメントを行うことが大事です。
最後に、「仕事は苦しいものだ」という思い込みです。仕事は楽しいものばかりでなく、当然、きつく大変なことの方が多くあります。一方で、苦しいだけで終始してしまうような仕事観は、特に若い社員の場合には響くことはないと言っても過言ではありません。例えば、「頑張っていればいつか何かが見えてくる」「お金を稼ぐのは苦しいものだ」といった考え方では、効率を考える若手社員は納得しないでしょう。苦しい思いをして貴重な人生の時間を費やすのであれば、他に行こうと考える人が増えているため、上司の皆さんには「大変さを乗り越えた先に手にできるもの」をしっかりと伝えることが求められます。
OJTをマネジメントと切り離して考えるのではなく、マネジメントの入り口と捉えて、一人ひとりの成長をいかにチームを成果へと導く個々の貢献へと繋げていくかを強く意識して臨むことがとても大事なことのように思います。
カテゴリー:人材育成
より効果的なフィードバックについて
2024年4月26日5:11 PM
フィードバックとは、組織、個人、プロジェクト、商品、サービス等のこれまでの成果や行動について、他者の評価を本人に伝えてアドバイスすることであり、個人についてであれば、メンバー一人ひとりの考え方や実際の行動に対して評価や指摘を行うことです。
フィードバックは、主にプロジェクト終了後の振り返りや人事評価等の実施後など、多くの企業で日常的に行われています。基本的には上司から部下に対して行われますが、リーダーからメンバーへ、先輩から後輩へ、同僚から同僚へ、メンターから新入社員へ行われることもあります。具体的には、チームの目標達成に必要な問題解決やメンバーの成長促進を目的とし、チーム全体やそれぞれのメンバーに対して、動機づけや軌道修正、補強改善を促すコメントを行うこととなります。一方で、単に「コメントを伝える~受け取る」だけでは、フィードバックの本来の目的を果たすことはできません。
効果的なフィードバックを行うためには、ポジティブなフィードバックとネガティブなフィードバックをうまく組み合わせて行うことが必要です。
まず、ポジティブ・フィードバックですが、単に褒めるだけではなく、感謝や労いの言葉、仕事の良い点、成長したと思える点などについて具体的伝えることで、メンバーが仕事に対して自信をもち、積極的に取り組めるように意欲付けを図ることを目的として行われます。ネガティブ・フィードバックを行う前に、まず良かった点を意識的に探して評価するポジティブ・フィードバックからすることで、メンバーがネガティブ・フィードバックを前向き受け止めやすい環境を作ります。
次に、ポジティブ・フィードバックとは逆に、ネガティブ・フィードバックで問題点や懸念点にフォーカスしていきます。本人が実際に行っていた行動のなかで、改善すべきポイントは何であったか、さらに上司として本人にどのようなレベルを期待しているのかの「期待値」を伝え、期待に応えるレベルに至るまでの本人の「現在地」を理解させ、「いま何が必要か」の対話をスタートさせます。問題が生じている原因を深く掘り下げていく効果があるため、失敗や間違いの自覚を促し、同じことを繰り返さないための対策を立てるのにとても効果的であり、受け取る側のメンバーからするとあまり好ましい内容ではないかも知れませんが、無ければ良いというものでもなく、むしろ本人の成長を促すためには必要不可欠なものと言えます。一方で、伝え方によっては単に批判、叱責されただけと受け止められてしまいかねず、モチベーションに悪影響を与える恐れがあるため、リスクを認識し、受け取る側のメンバー一人ひとりに合わせた伝え方の配慮が必要です。
このようにポジティブ・フィードバックとネガティブ・フィードバックをうまく組み合わせて伝えていくことで、より効果的にフィードバックを行うことができます。皆さんの職場ではどのようなフィードバックを行っていますか。
カテゴリー:人材育成
業務プロセスで繰り返される状況判断について
2024年3月26日12:21 PM
我々は意識、無意識にかかわらず、多くの判断を日々の業務の中で繰り返しています。そのため、より効果的な判断や決断が求められると同時に、それは選択を誤ればリスクを伴う可能性もある重要な行為とも言えます。一方で、チームメンバー一人ひとりの判断力や決断力が向上すれば、チーム全体の生産性が向上し、日常業務の遂行をスムーズにするだけでなく、チームの目標達成においても非常に効果が期待できます。
まず、何かを判断する際には、その裏付けとなる情報やデータが必要となります。過去から現在に至るまでの様々な情報やデータを整理し、そのうえで「だから、こう判断する」という、理由や根拠に基づいて客観的に行われます。例えば、出勤時に外に出たとき、空の様子が怪しかったとします。そこで、スマホで天気予報を確認し降水確率が高いという情報を得て、雨が降ると判断する、という感じです。つまり、判断とは、現状分析と情報収集に基づく頭の中の整理であり、既存の物事に対して評価をすることであるため、決定する対象は「現在」であり、その先の決断における検討材料の一つとも言えます。
次に、決断の対象となるのは、現在だけでなく「未来」に向けて及ぶものであり、決断されたことには必ず行動が伴います。先の例えで言えば、雨が降ると判断したことにより、傘を持っていくと決断する、というようなイメージです。これは、所謂「ソラ・アメ・カサ」という、論理的思考のフレームワークの一つでもあります。
さらに例えるなら、取引先から「商品の価格をもう少し下げられないか」との要望があった際、値下げすることによって、生じるメリットとデメリットを整理して値下げできると判断し、そこから、取引先との関係性や要望のレベル等を考慮して最終的に値下げするのか、しないのかを決断する、といった感じです。
一方で、判断するための条件や情報は揃っているのに、判断しないまま放置してしまっていたり、判断に基づかない決断をしてしまったりすれば、仕事が前に進まなくなるだけでなく、ケースによっては重大なリスクも伴いかねません。
そうしたリスクを抑止するためには、まず、目先の問題だけに意識が囚われていないかを疑うことが必要です。目の前に問題となって見えている事象だけに対処しようとすると、一見、問題が解決したように見えても、根本の阻害要因の排除や解消には至らず、結果的に却って手間やコストが増えてしまい、むしろ効率が悪くなってしまう事態に陥りかねません。誤った判断や決断をしないためにも、目先の問題だけに囚われないようにすることがとても大事です。
次に、自分一人で決められることなのか、自分だけでは決められないことなのか、の2つに振り分けて考えることです。自分一人で決められるのであれば、即座に判断、決断し、自分だけで決められないのであれば、誰の許可や判断が必要なのかを確認しスピーディに必要な行動をとることで、自分一人で決められるのにもかかわらず、初動で遅れをとってしまうような事態を防ぐことができます。
そして、「できるのか、できないのか」「やるべきか、やらないべきか」を考えます。まず、対象となる選択が「できるのか、できないのか」を判断します。さらに、「やるべきか、やらないべきか」については、どんな事案や問題だとしても、組織にも個人にも対応できることとできないことがあり、組織の企業理念や個人の立場、役割といった視点から判断されるため、実現可能であることと、やるべきかどうかは別の判断となります。もし、それが「できないけれど、やるべき」であったなら、実現不可能な理由を洗い出し、いかに可能にするかを検討するなど、シンプルでクリアな判断ができるようになります。
ビジネスの様々な場面で、時として難しい判断や決断を迫られることは屡々です。そうした際に、いかに最終的に自分で責任をもって主体的に物事を決めることができるかが、ビジネスパーソンには求められます。皆さんの職場はいかがですか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
チームの仕事の成功確率を高めるために
2024年2月27日11:54 AM
皆さんの職場のチームの仕事の成功確率はいかがでしょうか。仕事の成功確率を高めるためには、それぞれのメンバーが「いかに適切に状況判断できるか」、また「それについての最も適したアプローチをとることができるか」が求められます。
この2つを育むためには、まず、上司やリーダーがメンバーに問いかけ続けるという「問いの共有」を図っていくことが必要です。例えば、「クライアントやユーザーの満足度をもっと高めるためには、どう工夫すればいいのか」「チーム内の情報共有を徹底するためには、どんなルールが必要なのか」「作業工程のリスクを防ぎ、安全性を高めるためには、何をどうコントロールすればいいのか」などの課題をメンバーに問いかけ共有することです。
さらに、成功確率の高いメンバーへと成長するためには、仕事は結果で評価される一方で、安定的に結果を出していくためには、正しいプロセスで仕事ができるかがカギとなることを教えることです。
理想的なのは「良いプロセスで成功すること」、次に望ましいのは「良いプロセスで失敗すること」、そして「悪いプロセスで失敗すること」、最も良くないことは「悪いプロセスで成功してしまうこと」です。例え、悪いプロセスで成功したとしても、得てして結果オーライで済ませがちになり、「ツイていた」「運がよかった」と思い、軌道修正しないため、結果、悪いプロセスで失敗を繰り返すことになってしまいます。
そうした事を防ぐためには、目先の勝ち負けだけを見るのではなく、良いプロセスで仕事ができたかどうかを上司やリーダーが厳しく評価すること、また、そうした厳しい評価によって、最も良くない「悪いプロセスで成功してしまうこと」をフィードバックし、しっかりと内省を促し、軌道修正の機会を与えることがとても大切です。
チームの成果に責任をもつ上長として、メンバーに対して、結果を出すことは大前提である一方で、結果を出すことの重要性を伝えながらも、メンバーが良いプロセスでそこに向かっているかどうかを常に確認していくことは、上司やリーダーのとても大事な役割の1つではないかと思います。
カテゴリー:人材育成
これからの上司の在り方について
2024年1月30日11:05 AM
このブログをみていただいてる皆さんは部下をもつ上司やリーダー等の役割を担われている方が多いのではないでしょうか。
上司の役割は「チームの目標の達成」「意思決定」「部下の指導育成」「組織理念の浸透」など様々ありますが、このような一つひとつの役割の過程や結果においてその責を負うことが上司にとっての最大の役割と言えます。たとえ、タスクを部下に任せたとしても、そのタスクに対する過程、結果の責任は常に上司にあり、問題があれば上司はその責を負わなければなりません。もし部下がトラブルやミスを犯してしまった際、𠮟りつけるだけで上司がその責任を負うことをしないなら、上司の役割は果たしていないということになります。
そういう意味では上司はあまりいい役回りであるとは言えないのかもしれません。若いビジネスパーソンの中には責任が増すことを嫌がり、出世や昇進に消極的な方も少なくないようです。
チームをどのように運営し、その目標が達成され、さらに部下の育成が促進される環境を形成していくか。そのためには「仕事の意義と目的の理解の促進」「必要とされていることの実感演出」「キャリアプランの段階作り」を部下に波及していくことで、上司と部下との関係性を構築し、一人ひとりを活かすチームを作っていくことが求められます。
上司の皆さんにおかれては、上司としてそれぞれの上司像や考え方がお在りのことと思います。一方で、いまは当たり前と思われてきた従来のやり方では、その役割を果たすことは難しく、現代の若者を取り巻く環境と時代背景の変化の中で、上司自らがやり方を変え、この時代に適した部下とのコミュニケーションを設計する必要があるように思います。
良くも悪くも同質性が求められ、所謂「~すべき論」の教訓を受けて、部下がひたすらに指示通り働いていればいいという考え方の時代は終わり、これからは「多様性」や「創造性」が価値をもつ時代となり、部下一人ひとりの価値観を理解して個々の特性を伸ばし活かしていく事が求められています。そのためには、上司自身が自分と向き合って、どう変わっていけるかがカギとなります。
部下を伸ばすために、その「違い」を認め、立場で指示命令するだけでなく、部下が変わるの待つだけでなく、上司側が理解して積極的に部下に働きかけていくことが必要です。皆さんは、どのように思われますか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
職場の業務効率の改善について
2023年12月25日12:14 PM
皆さんの職場の業務効率はいかがでしょうか。前回ご紹介しました長時間労働の上限規制への対応のためにも、業務効率の改善は職場の必須の課題となっているのではないでしょうか。
そうした業務効率改善のための効果的な方法の一つとして「ECRSの原則」というものがあります。これは効率改善を実施する際の順序をまとめたものであり、Eliminate:排除「やめられないか」、Combine:統合「まとめられないか」、Rearrange:再編成「入れ替えられないか」、Simplify:簡素化「簡単にできないか」の頭文字をとった改善方法です。
ここで注意すべきは、「排除」⇒「統合」⇒「再編成」⇒「簡素化」の順番で進めていくことです。業務効率の改善を図ろうとすると、どうしても簡素化やマニュアル化等から着手したくなりがちですが、簡素化からスタートしてしまうと、もともとの業務に簡素化するための活動がプラスされて逆にタスクが増えてしまうことで途中で頓挫する可能性が高く、上手く行きにくい傾向があります。そのため、まずは「排除:やめること」から着手します。但し、「やめること」は今までの前例を覆すことでもありますので、個々のメンバーの判断で勝手に行うことはできません。そこで、上司やリーダーが主導して職場メンバーの意見を取り入れながら「やめること」を決めていくことがポイントとなります。
まず、「Eliminate:排除」ですが、各業務で行っている内容の具体的な理由や目的を洗い出します。もし明確な理由や目的が見当たらない場合、その業務は慣例化していただけという可能性が考えられます。ムダな業務を排除することで、パワーやコスト、時間を削減することができます。
次に、「Combine:統合」では、類似しているのに別々進めていた業務を一本化することで効率が向上できるかどうかを検討します。一方で、場合によっては分離されていた方が却って効率が良いケースもあるため、柔軟な考え方で取り組むことがポイントです。
三つ目の「Rearrange:再編成」とは、業務の順序や配置、場所、担当者等を入れ替えることで効率を向上できないかを検討することです。たとえ、短縮するタクトタイムが少なくても、長期的に捉えれば大きな業務改善やコスト削減に繋がります。
そして、最後に「Simplify:簡素化」です。業務の一部をパターン化、オートメーション化するなど、できるだけ単純で簡単な方法に変えることができないかを検討します。業務を簡素化することで、誰でも同じクオリティの作業ができるようになるため、業務の属人化の防止やミスの減少が可能となります。
業務タスクは時間の経過と共に増加し続ける傾向があります。そのため、半年ほどのペースでこうした業務効率を継続的に見直すことで定期的にタスクを減らしていくことが必要です。さらに、継続的な業務効率改善による長時間労働の是正が実現すれば、ワークライフバランスに優れた職場体制が構築され、離職率が低下することで将来の経営基盤の強化にも繋がります。皆さんの職場はいかがですか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
長時間労働の上限規制について
2023年11月27日11:13 AM
大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から働き方改革の一環として時間外労働の上限規制が施行されました。上限規制の時間は月45時間、年360時間で、臨時的な特別な事情がある場合でも、単月で100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内に収める必要があります。
一方で、建設業や自動車運転業、医療業では、時間外労働の上限規制の適用までに5年の猶予期間が設けられ、2024年4月からの適用となっています。こうした業種に猶予期間が設けられた背景には、長時間労働、休日出勤、人手不足という問題を早急に解決することが難しいと判断されたことがあります。
例えば、建設業界全体の労務課題としては、まさに「長時間労働」と「人員不足」が挙げられます。実際に、厚生労働省の2022年度の毎月勤労統計調査によると、建設業の1ヶ月あたりの総実労働時間は167.1時間と最も長時間であり、調査対象となっている全産業の平均137.3時間と比較して30時間も長い結果となっています。さらに、4週8休が充分に実施されていない傾向もあり、全体の約5割の工事が4週4休で動いているような状況です。
こうしていよいよ来年度から、全ての企業において働き方改革の法制が進み、時間外労働の上限規制が適用されたとしても、このような状況が改善されるかというと、そんなに単純にいかないのが現実ではないでしょうか。ただ単に、定時退社の徹底や有給休暇の推奨を行っても、それは帳尻合わせに過ぎず、仕事のやり方はそのままで、人員も増やすことが出来なければ、当然ながら管理職や仕事ができるリーダー的社員にしわ寄せが集中し、職場に歪みが生じてしまいます。
さらに、働き方改革に従った結果、本来、より多くの実務を経験してスキルアップしていくべき若い社員が早く帰り、すでに十分実務スキルを身に付けている管理職などへの負担が増すという矛盾も起きてしまいます。そうなれば、管理職は増々タスクの処理だけに忙殺されることになり、肝心のチームマネジメントや部下の育成まで手が回らず、心身共に疲弊していくのは時間の問題となり、そうした姿を見て、これから管理職になりたいと思う下の社員がいなくなってしまうリスクも伴いかねません。
こうしたリスクを避けるためには、単純に「とりあえずなんとかしなければならない」というような考え方ではなく、もっと本質的な業務改善による効率性の向上が求められます。皆さんの職場では業務効率の改善は進められていますか。業務効率改善については、次回のブログでご紹介したいと思います。
カテゴリー:雇用管理
管理職の育成に投資していますか
2023年10月26日10:21 AM
皆さんの企業では管理職層への育成活動は実施されていますでしょうか。
昨今の管理職は、多種多様な仕事に加え、働き方改革やパワハラ防止法の施行等を受けての職場改善への取り組みなど、明らかに過酷な状況に置かれていると思います。
グローバル化による企業間競争の激化のため、どの企業の管理職も厳しい目標に追いかけられる状況が続き、業務は増大し、部門マネジメントにじっくり取り組む余裕がないという状況です。さらに、少子高齢化による人手不足により、管理職としてよりプレイヤーとして活動しなければならないことの方が多く、結果、管理職が管理職として機能していないというケースも少なくありません。
このように管理職層が機能しないのは、個人の資質に問題があるとは言い切れず、単純に個人の問題として片ずけられない理由があると思います。
例えば、管理職への登用の際、プレイヤー時代に実務で優秀な成績を残した社員が抜擢されることが殆どで、昇進にあたって本来問われるべきマネジメントスキルが蔑ろにされてしまっているということが挙げられます。そもそも、管理職を登用する立場にある上司自身でさえ、マネジメントスキルを認められて上司なっているかわかりませんので、なんとなく自分の経験をもとに昇進させてしまっているという状況もあるのかも知れません。
こうした管理職は、マネジメントに関する教育を受ける機会や指摘をされる機会が少なく、実際にマネジメントが出来ているのか、出来ていないのかを自覚できずに、「マネジメントスキルが不足しているかもしれない」という疑問を持つことが出来ないということが実状です。
管理職になると組織における役割がこれまでと大きく変わるため、意識の改革が必要になります。そのため、管理職の役割をしっかりと理解、把握できているかが求められます。具体的には、管理職としてマネジメント業務の重要性を知ることや、コミュニケーションに関する考え方を変化させる必要があります。
一方で、こうした意識改革はいきなりできるものではありません。そのため、プレイヤーでいる段階からコーチングやリーダーシップ等のこの後のマネジメント業務に繋がっていくスキルについての教育の機会を計画的に提供することでスムーズなキャリアアップを目指していくことができる組織内の仕組み作りが大事です。当然、管理職になった後の定期的な学びの機会を提供することも重要です。
新人や若手への教育や育成活動は多くの企業で取り組んでおられると思います。ここで一度、管理職へのそれにも目を向けてみられてはいかがでしょうか。
カテゴリー:人材育成
新入社員が抱える悩みについて
2023年9月26日9:45 AM
早いもので今年度も半期を終えようとしています。毎年この時期は幾つかの企業で新入社員の皆さんへのフォロー研修をお引き受けしています。4月に入社した新入社員も入社半年が経つわけですが、ここにきて、いろいろ思いを馳せるタイミングにきていると思います。
一つは、人間関係ではないでしょうか。学生の頃は年齢差のない価値観の近い人たちとの付き合いで許されていましたが、社会人になると、年齢や考え方の違う広範囲な人たちとのコミュニケーションが求められます。目上や年上の方たちに対する言葉使いやマナー等を身に付ける必要があり、苦手な上司との関わりや取引先、関係者とのやり取りの難しさに悩みを抱える新入社員は少なくありません。
二つ目は、仕事についてです。新入社員には覚えなければならないことが山ほどあります。ビジネスマナーや1日のスケジュールなどに加えて、業務内容を覚えようとすると頭も体もいっぱいいっぱいになってしまい、さらに、「ミスをしたら叱られるのではないか」という不安も重なり、悩みを抱えてしまうというケースです。
三つ目は、環境の変化です。社会人になると生活環境が大きく変化します。プライベートの時間が少なくなったり、生活のリズムが大きく変わることで、不安を感じるようになります。特に、実家を離れて一人暮らしや寮生活になるとホームシックに陥ってしまう人も少なくありません。
皆さんもご経験があると思いますが、新卒の入社間もない頃は、いま思うとはっきりとした記憶がないほど無我夢中だったのではないでしょうか。一方で、ようやく周囲を冷静に見ることができるようになってきた入社半年というタイミングで先述のような悩み抱えることは屡々です。
こうした若い社員の皆さんに対して、日常の声掛けやOJTのプロセスでの適切なフィードバックとフィードフォワードによってフォロー、サポートし、積極的に関わっていくことが必要です。
超少子高齢化に突入しようとしているこの時代に若い人材の育成は、どの企業にとっても最優先の課題です。皆さんの企業ではどのように進められていますか。
カテゴリー:人材育成
ビジネスパーソンに必要な論理的思考について
2023年8月29日10:24 AM
皆さんの職場の社員の皆さんは論理的思考に基づいた行動ができていますでしょうか。ビジネスパーソンとしてキャリアを形成していくうえで、若手のうちに意識しなくても自然に論理的思考ができるようにしておくことはとても大事なことです。
論理的思考とは、複雑な事柄を整理してシンプルにしていく思考方法、物事を体系的に整理して矛盾や飛躍のない思考方法のことを言います。日々の仕事のなかには、実際に取り組むと様々なことが複雑に絡みあい、どこから手を付けたらいいのかわからないことがあります。そのような際に、論理的思考が役立ちます。ここで大事なことは、事の因果関係が整理できていて、ちゃんと成立しているかどうかです。一方で、論理的思考ができていないと、根拠がない個人の主観的見解に過ぎず、単なる思い付きと捉えられてしまったり、報告の際などには、上司から「結局、何を言いたいのかわからない」と思われてしまいます。
論理は、「前提」「推論」「結論」の3つの構成要素から成り立っており、論理的思考とは、「前提」と「推論」から「結論」を導く考え方です。論理的思考では、「結論」とその理由が必要であり、「推論」には「だから」「なぜなら」などの「結論」を導くための理由付けの役割があります。ここで注意すべきことは、ビジネスにおける「結論」の意味合いは学問的なそれとは違い、「結論」に「だから何なのか」というメッセージ性がなければ意味がなく、何らかの次へのアクションに繋がっている必要がるということです。
こうした論理的思考を日常的に特別意識することなくできるようになれば、コミュニケーション能力が向上し、相手の意見や考えを正確に理解することや自分の意見や考えを相手に理解してもらうことができるようになります。さらに、問題解決能力や提案力の向上も期待できます。論理的思考はビジネスパーソンにとって必要不可欠なスキルであり、あらゆる業務をこなす上でのベースです。皆さんの職場は、いかがですか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
最近の投稿
- 若手社員の早期戦力化について
- 社員の組織コミットメントについて
- 社員一人ひとりのリーダーシップの必要性について
- 人材育成の取り組みを戦略的に行えていますか
- チームを適切に機能させるタスク管理について
- ビジネスで重要視される目標設定について
- コンフリクトマネジメントについて
- チーム機能を高めるエンパワーメントについて
- 職場リーダーに求められる情況把握力について
- ビジネスパーソンに求められる計画力について
カテゴリー
月別アーカイブ
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)