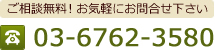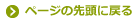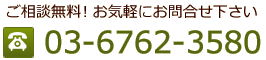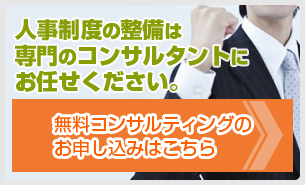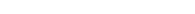株式会社マックブレイントップページ > 人事コンサルティングブログ > 人事コンサルタントの雑感
人事コンサルティングブログ人事コンサルタントの雑感 | 人事コンサルティングと人事制度に特化した専門企業【マックブレイン株式会社】の公式ブログ - Part 4
新年のご挨拶を申し上げます。
2018年1月4日11:35 AM
新年を迎えて皆さまのご発展とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
昨年は私共のブログをお読みいただき誠にありがとうございました。今年も皆さまのご活動のお役に立てるように下記のことを中心にこのブログに取り組んでまいります。
まず、多くの企業で眼前の課題に没頭しがちですが、もう少し先見性をもって取り組む必要があると思います。そのための必要な情報やアドバイスをできるだけ早く提供し、お役に立ちたいと考えております。
次に、これからのことをいろいろと考えると全体的に労働の生産性をもっと向上させることが必要ではないでしょうか。人手不足を補い、長時間労働の抑制や短縮を実現するためには、仕事のスピードや仕事の能率を上げると同時に、働き方の見直しや改革が必要です。このための情報やアドバイスも提供してまいります。
さらに、これからの大きな課題の一つとして、社員の人材育成とその確保が挙げられます。これからの困難な課題や新規の開発にチャレンジできる有力な社員の人材育成が変化していく経営環境を乗り越えるための不可欠な課題です。
この人材育成を多忙な環境の中でどのように促進していくことができるか。いろいろなテーマをもとに情報発信していくつもりですので、皆さまからもいろいろご意見をお聞かせいただきたいと思います。
さらにもう一つは、社内の人事管理の体制や制度の整備が不十分な企業が少なくないと思います。これらの体制や整備が不十分では、新たな事業へ着手しようとしても、その展開は行き詰ってしまいます。これらの点についても、このブログを通じていろいろ所見を綴っていきたいと思います。
今年も激動の時代が続き、多くの変化や変動が予想されます。いかなる時も後手に回らないように、そして、少しでも皆さまの経営活動にお役に立てるように取り組んでまいります。
どんなことでもお気軽にご意見やご相談をいただければと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
これからの人材育成は何を目標とするのか。
2017年12月18日12:58 PM
前回のブログでもお話しましたが、AIロボット等の技術革新により生じてくる社会構造の変化に対して、それに対応できる人材の育成が企業にとって重要な課題になってきています。
多くの企業や病院などからの私共への要請も従業員の人材育成指導が一番多いテーマになってきており、いままでは必要な知識技能等の研修指導が一般的でしたが、最近は社員の活動を根本から向上させる人材育成の依頼に変化してきています。
これは企業が社員に期待する役割や職務に変化が生じているためです。
これからの経営環境の変化に伴い、人間に期待される役割や職務は高度になり単純な作業や業務は技術システムなどに移行され、人の手で行うべきことは思考力や対話力といった人間本来の能力を発揮し、さらに先を見通して開拓していくような仕事になっていきます。
そのために必要な人材とは何か。それを見据えて具体的な人間像をより正確に掴んで人材育成に取り組むことが必要ではないかと思います。世の中の構造はこれからもかなり変わっていくと思います。
これからの人材育成のテーマを下記に幾つか例示しますので、ご検討いただければと思います。
①深い思考力や広い視野で総合的に判断できる人材を育てる
②新しい発想と豊かな開発力をもつ人材を育てる
③課題の解決に常に挑戦できるチャレンジ型の人材を育てる
④人間本来のコミュニケーション能力で常に組織をリードできる人材を育てる
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
現在の労働環境は、これからどのように変化していくのか。
2017年11月30日12:11 PM
これから労働環境はどのように変わっていくのか。皆さんはどのように思われますか。
これについては、いろいろな要因によって複雑に絡んでくるように思います。
一つは、人口の減少が依然加速し、労働人口は益々減少し人手不足が続きます。
一方で、正規雇用者と非正規の有期雇用者の賃金格差は依然として大きく、その格差が縮小していく傾向は殆ど見えてきません。
さらに、もう一つの大きな要因として挙げられるのが、AIロボットの伸びです。その見通しは人により差がありますが、ここ4~5年の間にも、かなりの分野で普及すると予想され、将来的には現在の人が行っている仕事の約3割ほどがAIロボットに移行するのではという推測もあります。
前述の3つの要因のみで、これからの労働環境を推測すると次のようなことが考えられます。
1)現在の人手不足はAIロボットの普及でかなり補充されていくことが予想されますが、急速なAIロボットの普及によって、広い分野の単純労働においての労働者の雇用(正規、非正規あわせて約3割ほどと予想)が奪われていくことが危惧されます。
2)一方で、主として正規雇用者で有能な中堅クラスの人材の育成と確保が不可欠で、これにより企業間競争の格差が表れてくると思われます。
3)同時に、企業経営においても、現在の単なる人手の確保からAIロボットの開発や活用に左右されるようになり、経営は一層の高度化が求められ難しくなり、人材育成の重要性も一層増してくるように思われます。
こうして考えてみると、今後10年、20年の尺度で国民総所得の再配分の仕組みについて、もっと社会的に見て、作り直していく必要があるように思います。
皆さんは、どのように思われますか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
労働の生産性をいかに達成させていくか【前回続き】
2017年10月31日6:09 PM
前回のブログで労働生産性の向上についてお話しましたが、まだ十分説明ができていないところもありましたので、前回にひき続き補足してお話させていただきます。
1)前回のブログで労働生産性の向上には、仕事のスピードや能率を上げることが必要であると述べましたが、単純に仕事のスピードを上げるだけでは労働生産性の向上はほとんど期待できません。
2)まず、部門全体の目標値を立て、それをもとに部署の仮目標を設定します。その上で各従業員が担当する主要ないくつかの業務について現状の仕事のスピードを時間で記録させます。これにより、まず各従業員に仕事の時間意識を強く持たせることから始めます。
3)上記の各人の現状調査からスタートし、段階を踏んで業務の内容や進め方の改善やムダな行動の削減、さらに有効なハード・ソフトの導入などを進めていきます。デジタルシステムなどのITの活用により、業務指示や必要な情報の迅速化や一体化され、業務事務量の大幅な削減が期待できます。
4)一方で、労働生産性の向上で得られた成果を長時間労働の削減や時差出勤、時間単位の有給休暇の採用などの様々な労働環境やさらには処遇へとつなげていくことで、さらに加速させて活動の相乗効果を上げていくことが大切です。
以上、一つの事例として必要な活動の概略を申し上げました。
労働の生産性をいかに具体的に達成させていくかは、どのような企業でも緊急の課題です。
私共は企業の業種や特性に合わせて、上記のような対策を総合的にまとめ、スケジュールを立て、それをもとにステップ毎に必要なプランやマニュアルチェック資料などを用意し支援指導に取り組んでいます。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
労働生産性を向上させるには、何が必要か。
2017年10月15日11:30 AM
ここ最近、労働生産性を引き上げようと取り組む企業が特に増えてきているように思います。その理由は、長時間労働を減らすと同時に人手不足を補うためには、一人ひとりの労働生産性の向上が必須だからです。
一方で、働き方を変えることで働く時間や働く場所を選択して働くことができるような奇抜な事例がありますが、これは一部の特殊な企業で採用していることで、働き方を変えることだけでは労働生産性の向上を図ることは難しいと思います。
労働生産性を引き上げるためには、時間あたりの労働生産性を向上させることを目標に取り組むことが必要です。仕事を時間で捉えること、仕事の時間意識を高めることです。
これからは仕事の質を維持向上しながら、同じ仕事でもできるだけスピードを上げて能率よく行うことが求められます。こうして仕事の質だけでなく、仕事のスピードを上げて時間あたりの仕事の量を増やすことにより、長時間労働の削減や人手不足対策に役立てることができます。
そのためには、まず仕事のスピードを上げるための新しい仕組みが必要です。それも一部の企業だけでできるようなものでなく、どのような企業でも行うことができる仕組みです。そして、そうした仕組みをいろいろと組み合わせて総合的に取り組むことです。
さらに、仕事のスピードを上げたことで不注意による仕事の質(品質やサービス等)の劣化を防ぐための仕組みも必要になります。
私共では、これらの仕組みや対策の構築に取り組んでおり、時短対策等の様々な仕組みや方法を構築してきました。事業の業種や企業の事情に合わせて、そのニーズにお応えします。ご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
人事管理は充分機能していますか。
2017年10月2日4:01 PM
人事管理は経営管理と表裏一体のものですが、皆さん企業の人事管理は充分機能しておられますでしょうか。
人事管理は会社にとっても、社員にとっても大事な役割を担う仕組みです。それが充分機能するための要素のチェックポイントを下記にいくつか挙げてみます。
▢賃金は経営成績と連動し社員への配分が適正に行われていますか。
▢毎年度の人事評価は経営の方向性と一体化していますか。
▢働き方の見直しは人事管理の見通しと連動して行われていますか。
▢社員の人材育成は正しい方向で進められていますか。
▢人材の活用は活かし切れていますか。
▢組織や要員管理は人事管理と連携して適切に行われていますか。
▢女性や高齢者の人材活用を人事管理によって充分バックアップできていますか。
▢採用は人事管理の中で一体に行われていますか。
こうしてチェックしていくと大事なところで社員の働き方ややる気を後押しするパワーが不足していて、経営の成果も充分出し切れていない状況が見えてくるのではないでしょうか。
たかが人事管理と思わず、少しでも見直されることでその波及効果は大きく期待することができます。
では、どのようなところから手をつけるべきなのか。
私共に一度ご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
働き方の改革は進んでいますか。
2017年9月15日4:40 PM
近く秋の国会において、日本の雇用慣行を見直すための関連労働法規の改正論議が始まります。
皆さんの企業では働き方の改革は進んでおられますでしょうか。
企業の現場では、新しい技術やサービスが次々に登場し、一方で消費社会もますます多様化し多くのニーズが要求されているなか、このような経営環境の中で従来型の固定的な仕事ばかりを続けていくことで良いのかと自問自答していく必要があると思います。
例えば、脱時間給についていろいろ議論されていますが、いままでの固定的な仕組みをはずし、時間に縛られずに新しい発想で働きやすい方法や環境を整備して成果を挙げることで大きく働き方を変えていくことができます。企業によっては、現行の労働法規である裁量労働制を既存制度と併せ、デメリット部分を抑制しながら進めることで成果を挙げています。
また、同一労働同一賃金の議論も多々なされていますが、正規社員と非正規社員の格差の現状がいつまでも続くとは考えにくく、社会的傾向として、いろいろとトライしながら現状の是正に努める企業が増えてきています。
来年度から労働者からの申し込みが始まる有期雇用社員の無期雇用化についても、本人の希望によりフルタイムで職務の範囲を拡げようとする社員等に対してその能力を評価し、正社員化や限定正社員化を積極的に行おうとする企業は予想以上に増えてきているように思います。さらに、有期雇用のままを希望する社員についても、非合理的な条件は削除し処遇の改善に取り組む企業が増加しています。
前回のブログでAIロボットの進化についてお話させていただきましたが、AIロボットが様々な職場で導入されても、AIを取り扱う社員の働き方が従来のままでは、結局何も変わらず現状は深刻化してしまいます。このようなAIを受け入れて使いこなす社員の人材の育成や確保は、これからの企業にとっての大きな課題であり、そのためにも一刻も早く働き方の見直し改革に積極的に取り組んでいくことが必要です。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
人工知能AIが急速に進展してきています。
2017年9月1日12:18 PM
6月の厚生労働省の発表によると7月の有効求人倍率は、バブル期を超える1.52倍で5ヶ月連続で上昇を続けており、一方で総務省発表の7月の完全失業率は、2.8%と6月から横ばいとなっています。さらに、正社員の求人倍率は、人手不足が進む中、企業は将来を見越して正規雇用の社員を増やす傾向にあり、統計開始以来初めて1倍を上回る1.01倍となっています。
こうしたデータは以前のブログのなかでもご紹介しましたが、この一方でAIロボットの開発が急速に進んでおり、自動車が自動運転で街を走るようになるなど、日常生活や経済活動にAIが導入されるようになり、その導入のスピードによっては2025年頃から一部の産業で人手余りが発生するのでは、との予想を一部調査機関が発表しています。
AIとAIロボットの進展スピードの予測は、様々な要因が絡んで進んでいくため、その予測の幅が大きく、確定的な予測は見えてきませんが、これからの大きな動向として注目していく必要があると思います。
既に、建築現場の重機や製造業の組み立てや加工作業、流通業、サービス業、さらには事務系の一部の定型的業務や作業などに進出しています。
こうした状況をみると、AIやAIロボットの技術進化による新しい産業革命の波が到来するように思われ、これに伴い、経営環境や企業間の競争も変化し、さらに厳しくなってくるのではないかと予想されます。
身近な現状の人手不足だけにとらわれて、将来の展望を読み誤ると大きな誤算を招きかねません。どのような企業でも、将来を見据えて経営や事業の展開に取り組むと同時に、このようなAI等の急速に進展するテクノロジーをどのように活かしていくか、どのように使いこなしていくかの課題にも取り組む必要があります。こうした課題は、人間サイドの課題であり、これに総合的に対応できる人材の育成や確保こそが今以上に経営上の重要な課題になってくると思います。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
人手不足が正社員に波及しています。
2017年7月31日4:29 PM
厚生労働省の発表によると2017年6月の正社員の有効求人倍率は、1.01倍となり、2004年の調査開始以来初めて1倍を超えました。さらに、パートタイマーを含む有効求人倍率は1.51倍で、バブル期で最も高かった1990年7月の1.46倍を上回っています。
働き手を確保しづらい環境の中で、企業にとっては、さらに正社員の確保が困難になってきており、内閣府の調査によると非正規社員から正社員へ転換を希望する比率は、非正規社員の3.6%で、ここ3年ほど横ばいです。このため、正社員の獲得競争がさらに激化し、一方で正社員の転職者の賃金が前職と比べて上昇するという傾向が続いています。
こうした環境の中で、正社員を確保し、さらに人手を充足させていくためには、どうしていくべきか。それぞれの役割を担う社員に対し、これから何を期待し、どのように向き合っていくべきか。構造的に全体を考えてみる必要があります。
実際に、なくてはならない大事な社員が退職したことで、そのマイナスを充足できずに廃業してしまう会社もあるようです。こうした状況下で、この経営環境にただ流されるのではなく、率先して先見性をもって対処していくことが必要です。
いまの人手不足の経営環境を将来への発展のチャンスととらえて、社内の経営改革をはじめ、職場環境の改善や社内の人材の育成や活用の徹底、働き方改革、そして社員の納得性のある適切な処遇改革などを積極的に、かつ、できるだけ早く進めていってほしいと思います。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
人手不足の対策は進んでいますか。
2017年7月15日1:38 PM
ここへ来て、人手不足が深刻化しており、このままいくと企業によっては更に厳しい状況になりそうです。そこで、このような状況を逆にチャンスに変えて、そこでできることから対策を立て、経営を改善していくことをおすすめします。
まず、会社も社員も思い切って、できるだけムダな仕事を取り除いていく運動を始めます。状況によっては、3割以上もの仕事の行動がムダとして発見されることもあります。そして、会社も社員も仕事のスピードや能率を上げて長時間労働を改善するための工夫や過剰なサービスをやめるなど営業活動を効率的に進めるための工夫に率先してチャレンジすることです。
もう一つは、勤務条件の見直し改善です。勤務時間も時差出勤や在宅勤務など、できることから進めていかれたらどうでしょうか。
この二つを他の企業よりも早く実行することです。そのメリットは社内外ともに大きく、求人活動や社員のやる気アップに好影響を与えます。そして、この二つの対策を進めていくための仕組みさえあれば、この程度のことはすぐにでも実行可能です。
私共は、こうした仕組みの整備に日々取り組んでいます。ご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
派遣社員が派遣先の正社員に移籍する動きが増えてきています。
2017年5月1日5:04 PM
派遣元企業にとっては登録している人材は大事な収入源であり、いままではそうした人材の引き抜きを拒否していましたが、2015年の労働者派遣法の改正により、この状況が変わってきています。
派遣元企業が職業紹介事業の許可を得ることや派遣先企業が派遣元企業に紹介料を支払うことなどでその移籍がトラブルなく行われるように施行規則(2015年労働者派遣法施行規則22条)が公認されたことにより、この求人難の状況下で派遣労働者の正規社員への移籍登用に拍車がかかったものと思われます。
派遣元企業でも派遣先との契約で派遣労働者の直接雇用は別途協議し紹介手数料を支払うなどの条項をはっきり示しているところもあり、この人材難の時代を考慮して派遣事業という人材紹介事業の担い手として派遣労働者のキャリアアップを後押しし、国の施策に沿って取り組む方向に進んできているのだと思います。
この動きは、大手企業のみならず中小企業にとっても優秀な人材確保のための有力な手段となってきているように思います。派遣社員の中には、運悪く就職難の時代と重なって派遣社員になっている優秀な人材も多く、この新しい移籍登用ルートによって、正規社員になるチャンスが増えることが期待されます。
さらに、厚生労働省では、派遣社員を含む有期契約労働者等を正規社員として雇用した企業に対して、一定の要件でキャリアアップの助成金の支給を行っており、この動きを後押ししています。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
企業で最も困っていることは何か。そして、それはどのように変化していくのか。
2017年4月16日12:53 PM
いま、何処の企業でも困っていることは人材の不足なのではないでしょうか。
特に困っているのはサービス業や小売業、流通業といった業種ですが、一般の製造業や建設業でも人材不足は深刻になってきています。
その原因はどこにあるのか。景気が数年前に比べて上向いていることも要因の一つですが、主な要因は人口の少子高齢化です。高齢者の人口割合は、現在27%を超え過去最高になっています。その高齢者の就労意識は向上してきていますが、65歳定年後の増加は極一部で限定的です。
一方で少子化の人口減少傾向は続いており、昨年一年間(2016年10月時点)の総務省の推計では過去最高で29万6千人の減少で、さらに現在高齢者の増加と出生数の減少傾向は変わらず、労働の担い手となる15歳~64歳の「生産年齢人口」は前年比で72万人減少しています。この生産労働人口の減少をどう補っていくのかが大きな課題となっています。
ひとつは、先ほど述べた高齢者の就労促進と女性の社会進出への期待ですが、これでどれだけ補充できるかというと、多くのネックとなる壁が存在していて、これだけでは到底補いきれない状況です。
次に、外国人労働者への期待があります。これも2016年10月の推計で外国人の人口数から出国数を差し引いた「純流入」が13万6千人で2015年の実績を4割上回り、過去最大になっています。しかし、人口の減少を外国人の受け入れで補充しようとすると、大規模な移民の流入が必要で、これもいろいろと障壁が多く限界があります。
もう一つの可能性は、今いろいろ言われている作業AIロボットへの期待です。確かに医療や生産工程、介護さらに建設現場、調査分析、あるいはサービス業、流通業などの多くの分野で導入され普及する時代がくると思います。しかし、これがどの企業でも人材不足の打開策として使われるようになるには、まだかなりの技術の蓄積と試行過程が続くように思われます。
こうしてみると、これからも企業の人材不足は続き、社会的には労働の流動性も高まり、どの企業でも人材の確保とそれを有効に活用できる職場作りを続けることが最大の課題になるに違いありません。そしてこのためには、従来の経営の仕方から脱皮し、社員をもっと直視し、もっと入念な対応と新しい仕組みを創出していく必要があると思います。
いまだ従来通りのルールや古い仕組みや制度のなかで社員を働かせている企業は多いのではないでしょうか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
働く社員の生産性をあげる議論をもっと広げよう。
2017年4月1日3:50 PM
今回のブログのテーマは、「働く社員の生産性を上げよう」です。
政府の働き方改革の議論では、これが不足しています。長時間労働を減らすことも残業時間に上限時間を設けて規制することも、正しいことに間違いはありません。
しかし、これから少子化によって、毎年50万人もの労働人口が減少していくといわれている状況で労働時間の規制などばかりに議論が集中し、肝心な企業内での従業員の労働生産性が取り残されているような状態では、企業もそこで働く人たちも全く報われません。
働く従業員一人ひとりの労働時間とパワーの生産性が上昇し、企業もそれをもとに成長戦略に手を伸ばせるようにしなくては、働き方改革の議論は成功していかないように思います。働き方改革の議論のポイントはそこにあると思いますが、皆さんの企業や職場ではどうでしょうか。
そこに働く従業員も自分の時間や能力の生産性をもっと引き上げることができなければ、労働時間が短くなるだけで、さらに人も減っていきますので、自分の仕事を充分消化できなくなります。企業にとっても、非正規社員の賃金も含めて賃金を増やそうにも、そこで働く人たちの生産性が上がってこないようであれば、続けていくことができなくなります。
そこで、私共は企業やそこで働く人たちの身になってどのようにこのような状況を打開し、取り組んでいったら良いのかを常に議論しており、このままにしておくわけにはいかない課題であるとつくづく実感しています。
いまだ企業の皆さんの中には、今一つ静観気味のところもあるのではないでしょうか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
現在の人事制度を一度見直してみませんか。
2017年3月15日5:04 PM
最近、人事制度の見直しの案件が非常に増えています。
少子高齢化に伴い若年層が減少し、高齢者の雇用の範囲が広がり雇用期間も長くなってきています。このためにも、社員の働き方を変えるには現行の人事制度の見直しが必要です。
ホワイトカラーの社員の状況を見ると仕事のスピードが遅く、能率も全体に低い状態です。多くの企業で能力重視の人事制度を採用しています。そのため、一般的な共通の能力要件による年功型の制度により、それぞれの社員の労働生産性の意識について充分ではありません。
さらに、社内の人材育成が思うように進んでいないため、社員の知識は豊富でも、それを必要な仕事の技能レベルにまで引き上げ、仕事に充分活かすことができる状態になっていません。これは、上司や上級者が日常の仕事の中で部下や下級者を直接指導し、自らも成長できる仕組みができていないからです。
このような状態を打開していくことが、社員の働き方を変えていくためには必要です。上記のような人事制度や人事管理の内容を少しでも変えることで、社員の働き方を変えることができます。私共は、こうした人事制度の補強改善をご希望に沿いながら行っています。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
いまの人手不足をどのように乗り越えるか。
2017年2月27日7:06 PM
増々、人手不足の構造になってきています。皆さんの企業ではどのように対処していこうとしていますか。
今までと同じように勤務条件などの職場環境も変わらず、相変わらず長時間労働で残業が続いていくようであれば、従業員も先が見えず行き詰ってしまいます。勤務条件などは早く見直す必要があります。
求人活動も同じで、毎年同じように新卒の求人に終始するのではなく、新しいターゲットを開拓しチャレンジ意欲のある新しいパワーの獲得を目指す必要があり、毎年新卒内定者に辞退されるような状況が繰り返されていては、これも先が見えてきません。
さらに、人手不足の構造に対処するためには、社員の働き方を変えていく必要があります。そのためには、その上司である管理職の人たちの指示の仕方から働き方、指導の仕方などを変えていかなければ不可能です。私共は、働き方を変えるための管理職に向けた集中研修を行っています。
さらにもう一つは、会社の規定やルールをはじめ、人事制度などを従来型のものから新しい対応ができる制度に変えていくことが必要です。
多くの企業で職能等級型の人事制度により、共通の職能要件での年功序列型の勤務が長年続いてきたために、社員一人ひとりの労働生産性が停滞している状況が見られ、もっと全体にスピードを上げ、能率を上げることが出来るようにしていかないと人手不足の構造への対応が追い付いていきません。私共は、このような企業の人事制度を短時間で効率的に見直しする活動を進めています。
人手不足の構造にどのように対応していくか。このためには上記のような対策が不可欠です。皆さんの企業ではいかがでしょうか。一度ご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
残業時間の上限規制の原案、月60時間に決まる。
2017年1月31日10:04 AM
いまの労働基準法では、1日の労働時間は8時間まで、1週間では40時間(特例事業場は44時間)と定められています。しかし、労働基準法36条(サブロク協定)に基づき、労使協定を結んで特別条項を付ければ無制限に残業を続ける事ができてしまうのが現状です。
この残業時間の無制限の状態については、長い間いろいろな議論がされてきましたが、政府は「働き方改革」として残業時間の上限を月60時間に制限する上限規制の原案をまとめ、年内に労基法の改正案が国会に提出される予定ですが、その法制化には今年いっぱい掛かりそうです。
いずれにしても、やっと残業時間の青天井の状態に歯止めを設けることができそうです。
しかし、その内容を見ると特定の時期に忙しい企業には1か月のみ100時間、前後の2か月は80時間まで残業を認める案が検討されているようで、この繁忙期措置についてはもっと配慮してほしいという意見もあり、一方でそもそもの上限規制を月40時間ぐらいのより厳しい上限の法制化を求める声もあります。
これから、この長い残業時間の問題を社会全体がどのように捉え、取り組んでいくべきかです。
企業によっては、事業の転換もできずに厳しい経営状態の中で死活問題として苦しんでいる企業もまだ多く存在し、さらに、この残業時間を含む長時間労働の問題については、多くの企業で先が見えない状態になっていることが現状です。しかし一方で、それを乗り越えてこの問題に取り組んでいる企業もあります。
いずれにしても、この残業時間の問題については、労基法による上限規制だけでなく、どの企業も早く脱却し、従業員の総力を活かして活動できる企業に再生するための対策を真剣に考えていくことが必要であると思います。皆さんの企業では、どのように考え、取り組んでおられますか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
今年は働き方を変えて社員のトータルパワーアップに努めよう。
2017年1月14日7:02 PM
今年はさらに変化の激しい年になりそうです。そうした中で少子高齢化の経営環境で求人難が続きます。そこで今年はできるだけムダな仕事は止めて、さらに働き方を変えて社員のトータルパワーアップに努めていこうではありませんか。
まず、ムダな業務を取り除くことです。ムダな仕事と一言でいっても、主に仕事の方法ややり方がムダなことが非常に多く、それらを合計すると企業によって違いますが平均するとおおよそ2割近くがムダな作業といわれています。
さらに大きな課題は、働き方が従来のやり方から脱皮できず非能率のままになっていることです。特に、事務管理部門のホワイトカラーの職場や製造業以外のサービス業や小売業、建設業などの業種では労働生産性が非常に低い職場が多く見受けられます。
これらの働き方を変えていくことで労働生産性は、3割~4割を改善できるといわれています。この改善ができれば、深刻な労働災害まで発生している長時間労働も解消でき、ワークライフバランスも経済全体も上向き、明るい社会の実現も不可能ではありません。これを社会全体のゴールイメージにしようではありませんか。
私共は、このゴールイメージの達成に少しでも寄与するための新しい仕組みやツールの作成に取り組んでいます。当ホームページに掲載しておりますので、参考にしていただければ幸いです。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
新年のご挨拶を申し上げます。
2017年1月3日1:18 PM
新年を迎えて皆様のご発展とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
昨年は、私共のブログをお読みいただき誠にありがとうございました。
今年も皆様の活動を支援するため下記のことをモットーに取り組んでまいります。
まず、皆様の企業の活動に必要な新しいニュースや情報をできるだけ早くお伝えします。
昨年は、今までの仕事の働き方を変えるにはどうしたら良いかとか、労働の生産性の向上や同一労働同一賃金のテーマ、それに長時間労働の問題などがテーマとなりました。今年も少子高齢化の雇用環境等を背景に厳しい経営環境の中でさまざまなニュースやテーマが起きてくると思われます。
さらに、上記のほかにも皆様の企業活動に参考となるいろいろな情報をできるだけ取り上げて提供します。今年は、労働法規やいろいろな基準やルールの改正が行われていくと思われますので、それも積極的に取り上げて漏れの無いようにご報告してまいります。
同時に、それらに合わせて私共の私見として、それぞれにどのように対応することが必要かなどのアドバイスやコメントを発信していきますので参考にしていただければ幸いです。
今年は、昨年以上に国内外にわたって多くの変動や変化が予想されます。
皆様の企業活動に少しでも貢献できるように取り組んでまいりますので、どんなことでもお気軽にお問合せいただければと思います。当ホームページの無料お問い合わせフォームより、ご意見等を含めて何なりとお寄せください。
今年もよろしくお願いいたします。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
長時間労働から早く脱出しよう。
2016年12月15日4:30 PM
いまだ多くの企業で長時間労働が続いていますが、一日も早くそこから脱出することが必要です。長時間労働は多くの損害やデメリットを企業に与えており、それでもそれから脱出できない企業が多いのが現状です。
その理由の一つは、短い納期に強いられる企業の現状があります。それともう一つは、36協定により実際には無制限で残業が可能であるという労働法規の欠陥です。このような先進諸国では例を見ない規定がいまだに残っているという事です。前者の理由がなせる事由でこのような法規がいまだに残っていますが、来年にもこれに歯止めをかける労働法規が制定されるのではないかといわれています。
課題は、どのようにすれば実際に長時間労働から脱出できるかです。勤務時間を短縮するだけでは問題の解決にはなりません。長時間労働が発生する根本原因をもとにその構造的な企業の体質を変えることです。
その体質を変える唯一の指標は、従業員一人ひとりの労働生産性を改質することにあります。それぞれの企業の体質によっても異なりますが、おおよそ10~40%程度の改質が必要と思われます。
そして、これをどのような方法・手段で達成するかですが、人の体質の改善と同じで総合的な対策を動員して行うことが必要です。
私共は、これらの企業診断とそれにより摘出した要因に対し総合的な処方箋を作成して対処し、さらに必要な期間をもとにバックアップを行って解決しています。
いずれにしても長年の慣行や習慣のもとに行われてきた従業員の働き方をどのように変えていくかです。
一度、私共にご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
トータルパワーアップの推進を目指そう。
2016年10月16日6:16 PM
今や業種業態にかかわらず、どのような企業でも従業員のトータルパワーアップを一層推進していかなければならない経営環境になっていると思います。しかし、そうした状況にもかかわらずトータルパワーがフルに発揮されている企業は非常に少ない状況です。
その理由がどこにあるのか。皆さんの企業でも各部門部署の社員の働き方を検討してみてはいかがでしょうか。その場合の社員の行動に対するチェックポイントを下記に挙げてみます。
①仕事の進め方がマンネリ化していないかどうかの見直しを行っているか。
②ムダな仕事が発生しているのに相変わらず同じように進めていないか。
③仕事の能率を上げるように社員一人ひとりが心がけて実行しているか。
④どんな仕事でも少しでも時間を短くして仕事の成果を上げることを心がけて実行しているか。
⑤皆で協力してやれば効率よくできることを一人で進めていないか。その逆の場合も同様に協力の仕方の見直しを行っているか。
次に組織に対するチェックポイントを下記に挙げておきます。
①組織が固形型の組織(従来の固形型の組織)のままではないか。新しい仕事に適応できる柔軟な組織になっているか。
②勤務時間や勤務の方法などの勤務条件について人と仕事を軸に見直しを行っているか。従来の管理型の勤務条件のままになってはいないか。
③長時間労働を減らし、社員の創意工夫とチャレンジをもって新しい仕事の仕方に向かっているか。
④人材育成を仕事と一体化した人材の活用と連動して進められているか。
⑤部門部署における的確な要員管理と人材の適正配置によって組織のトータルパワーアップが図られているか。
上記5項目のいずれの項目もそれを達成するためには、いろいろな仕組みやプロセスが不可欠です。同ホームページ内のコンサルティングサービスの欄でこれらの内容を紹介しておりますので参考になさって下さい。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
最近の投稿
- 若手社員の早期戦力化について
- 社員の組織コミットメントについて
- 社員一人ひとりのリーダーシップの必要性について
- 人材育成の取り組みを戦略的に行えていますか
- チームを適切に機能させるタスク管理について
- ビジネスで重要視される目標設定について
- コンフリクトマネジメントについて
- チーム機能を高めるエンパワーメントについて
- 職場リーダーに求められる情況把握力について
- ビジネスパーソンに求められる計画力について
カテゴリー
月別アーカイブ
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)