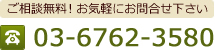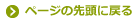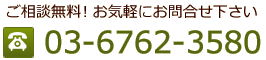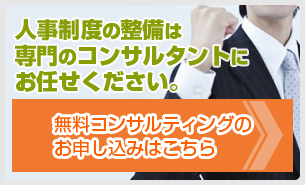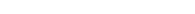株式会社マックブレイントップページ > 人事コンサルティングブログ
人事コンサルティングブログ
新年のご挨拶を申し上げます。
2017年1月3日1:18 PM
新年を迎えて皆様のご発展とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
昨年は、私共のブログをお読みいただき誠にありがとうございました。
今年も皆様の活動を支援するため下記のことをモットーに取り組んでまいります。
まず、皆様の企業の活動に必要な新しいニュースや情報をできるだけ早くお伝えします。
昨年は、今までの仕事の働き方を変えるにはどうしたら良いかとか、労働の生産性の向上や同一労働同一賃金のテーマ、それに長時間労働の問題などがテーマとなりました。今年も少子高齢化の雇用環境等を背景に厳しい経営環境の中でさまざまなニュースやテーマが起きてくると思われます。
さらに、上記のほかにも皆様の企業活動に参考となるいろいろな情報をできるだけ取り上げて提供します。今年は、労働法規やいろいろな基準やルールの改正が行われていくと思われますので、それも積極的に取り上げて漏れの無いようにご報告してまいります。
同時に、それらに合わせて私共の私見として、それぞれにどのように対応することが必要かなどのアドバイスやコメントを発信していきますので参考にしていただければ幸いです。
今年は、昨年以上に国内外にわたって多くの変動や変化が予想されます。
皆様の企業活動に少しでも貢献できるように取り組んでまいりますので、どんなことでもお気軽にお問合せいただければと思います。当ホームページの無料お問い合わせフォームより、ご意見等を含めて何なりとお寄せください。
今年もよろしくお願いいたします。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
長時間労働から早く脱出しよう。
2016年12月15日4:30 PM
いまだ多くの企業で長時間労働が続いていますが、一日も早くそこから脱出することが必要です。長時間労働は多くの損害やデメリットを企業に与えており、それでもそれから脱出できない企業が多いのが現状です。
その理由の一つは、短い納期に強いられる企業の現状があります。それともう一つは、36協定により実際には無制限で残業が可能であるという労働法規の欠陥です。このような先進諸国では例を見ない規定がいまだに残っているという事です。前者の理由がなせる事由でこのような法規がいまだに残っていますが、来年にもこれに歯止めをかける労働法規が制定されるのではないかといわれています。
課題は、どのようにすれば実際に長時間労働から脱出できるかです。勤務時間を短縮するだけでは問題の解決にはなりません。長時間労働が発生する根本原因をもとにその構造的な企業の体質を変えることです。
その体質を変える唯一の指標は、従業員一人ひとりの労働生産性を改質することにあります。それぞれの企業の体質によっても異なりますが、おおよそ10~40%程度の改質が必要と思われます。
そして、これをどのような方法・手段で達成するかですが、人の体質の改善と同じで総合的な対策を動員して行うことが必要です。
私共は、これらの企業診断とそれにより摘出した要因に対し総合的な処方箋を作成して対処し、さらに必要な期間をもとにバックアップを行って解決しています。
いずれにしても長年の慣行や習慣のもとに行われてきた従業員の働き方をどのように変えていくかです。
一度、私共にご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
複線型人事制度で人事の停滞を解消しよう。
2016年11月29日12:24 PM
求人難の時代になって、社内の人材をフルに活かしていかなければならないのに、人事が停滞していて思うように活性化が進まないことをお悩みの企業が多いように思います。皆さんの企業ではいかがでしょうか。
そこで、お勧めするのが複線型人事制度の採用です。
複線型人事制度の良さは、従来の固定的な職制に対してもう一本別の職制を設けて人材を幅広く活かすことができる制度です。
その例をいくつかお示しすると次のとおりです。
例1.現在存在する管理職・中堅職・一般職のキャリアコースの管理職の階層に併行して、もう一つ専門職のコースを新たに設けて管理職と専門職で相互に条件を設定して異動できるようにします。これにより、管理職のコースで人事の停滞が起きている場合、専門職との相互異動によって解消することができ、さらに専門性や専門能力を活かした専門職としての活動を期待することができます。
例2.中堅職層でも総合職と専任職の複線型にすることで、総合職は課題解決などの総合的な役割に従事し、専任職は従来の担当職務に従事する。などのように役割職務の範囲を複数にして、それぞれの担い手としての人材育成としても役立ち、処遇も行いやすくなります。同じく一般職についても、従来の実務職の業務と総合職の役割に分け、採用も複線型で行うことでより効率的な採用活動が可能になります。
上記の例は、従来のキャリアコースにもう一本複線化する制度であり、業種によっては多くの複線化を行っている企業もあります。まずは一本の複線化だけでも現状の人事の停滞の解消や必要な人材育成などに役立ちます。
複線型人事制度については、コンサルティングサービスの資格制度の欄にも掲載しておりますので、是非参考にしていただければと思います。
カテゴリー:資格制度
最近の賃金の議論について
2016年11月14日6:41 PM
最近、また賃金についての議論で賃上げが中心になって行われていますが、実はそこではなく、賃金についての議論は賃金の本質を見直すことにあると思います。賃金が働く従業員たちの活動や労働の対価として適正に行われているかです。
一つは、賃金は、その適正の対価として従業員にわかりやすく、従業員の意欲や成長を促す制度として適正な配分で行われているかです。
もう一つは、賃金は企業の経営成績に連動して経営成績が上向けば増え、逆に下向けば減るように、その構造や仕組みのもとに賃金が適正な配分で行われているかです。
しかし、経営成績が上向いても賃金の上昇がいつの間にか適正な配分でなくなっていたり、逆に経営成績がかなり落ちていても無理をして賃金を支払い続けていることが往々にして行われています。
賃金は、経営成績に連結しています。経営に許容される人件費で適正に配分され、それをもとに行われるべきものです。しかも、その経営成績は経営者と従業員が一体になって努力した結果です。そのためにも前述に話したように従業員にわかりやすく理解される賃金として認められ、それによって経営成績に連結した賃金として適正に支給されるものであることが必要です。
政府が毎年度のように企業に対し賃上げ要請をしても無理なことは無理ですし、企業にとっては、賃金の本質と有るべき賃金の構造をもとに従業員と共に経営の発展に努め、それを経て得た経営成績をもとに、見える化して適正な賃金管理をすることが重要です。
皆さんの賃金の本質とはどこにありますか。
これだけでは、まだ十分なお話ができていないと思いますが、今回はこのくらいにしてまたの機会にお話しさせていただきます。
カテゴリー:賃金制度
非正規社員の賃金制度を見直そう。
2016年10月31日5:48 PM
非正規の雇用は、現在雇用総人口の約4割に達しています。非正規社員には、非正規の所謂スタッフ社員、派遣企業から派遣される派遣社員、さらに臨時雇用のアルバイト社員など多数の社員がいます。
これらの非正規社員の賃金制度をどのように見直すべきかがこれからの課題の一つになっています。政府では、いま一億総活躍社会のスローガンのもとで非正規社員の賃金制度の見直し論議が行われています。
これからは、従来の非正規社員の使い方から脱皮して重要な人的資源として確保し、そのパワーアップを図りつつ雇用を維持していくことが求められます。そのためには、非正規社員の賃金制度を正規社員のそれと合わせて見直していくことが必要です。
非正規社員の賃金は、おおむね単一職務による職務給の賃金ですが、多くの企業で、正規社員の賃金はおおよそ職務遂行能力をもとに勤務年数とともに定期昇給が行われており、担当の役割職務に必ずしも直結しない職能給賃金制度です。しかし、これには、さらに担当する役割職務の基準を加えて、その評価によって賃金の算定が行われるように段階を踏んで改正していく必要があります。
一方で非正規社員の賃金も正規社員と同様にそれぞれの担当する役割職務の達成度に加え、能力要件等の基準も加えて評価し、算定できる賃金制度にしていくことが必要です。
賃金の算定には、勤務地や勤務時間等の勤務条件がありますが、これからの基準は、正社員、非正規社員とも同じ基準を適用することです。正規社員の中にも勤務地の限定や勤務時間の短縮を希望する社員も増えてきています。非正規社員にも単一の同じ職務を短時間勤務で続けることを希望する者もいれば、中には職務を広げてチャレンジしようと能力アップにも取り組んでいる有能な社員も多くいます。
これらを同じ算定基準でそれぞれの働き方をもとに賃金を算定することで、正規と非正規の間を納得のいく合理的な条件で移動が行われるようにすることができれば、新しい時代に向かって一歩前進なのではないでしょうか。
私共は、それぞれの企業のご要望やお考えをお聞きしながら、どのように賃金制度を作っていくかに取り組んでいます。
カテゴリー:賃金制度
トータルパワーアップの推進を目指そう。
2016年10月16日6:16 PM
今や業種業態にかかわらず、どのような企業でも従業員のトータルパワーアップを一層推進していかなければならない経営環境になっていると思います。しかし、そうした状況にもかかわらずトータルパワーがフルに発揮されている企業は非常に少ない状況です。
その理由がどこにあるのか。皆さんの企業でも各部門部署の社員の働き方を検討してみてはいかがでしょうか。その場合の社員の行動に対するチェックポイントを下記に挙げてみます。
①仕事の進め方がマンネリ化していないかどうかの見直しを行っているか。
②ムダな仕事が発生しているのに相変わらず同じように進めていないか。
③仕事の能率を上げるように社員一人ひとりが心がけて実行しているか。
④どんな仕事でも少しでも時間を短くして仕事の成果を上げることを心がけて実行しているか。
⑤皆で協力してやれば効率よくできることを一人で進めていないか。その逆の場合も同様に協力の仕方の見直しを行っているか。
次に組織に対するチェックポイントを下記に挙げておきます。
①組織が固形型の組織(従来の固形型の組織)のままではないか。新しい仕事に適応できる柔軟な組織になっているか。
②勤務時間や勤務の方法などの勤務条件について人と仕事を軸に見直しを行っているか。従来の管理型の勤務条件のままになってはいないか。
③長時間労働を減らし、社員の創意工夫とチャレンジをもって新しい仕事の仕方に向かっているか。
④人材育成を仕事と一体化した人材の活用と連動して進められているか。
⑤部門部署における的確な要員管理と人材の適正配置によって組織のトータルパワーアップが図られているか。
上記5項目のいずれの項目もそれを達成するためには、いろいろな仕組みやプロセスが不可欠です。同ホームページ内のコンサルティングサービスの欄でこれらの内容を紹介しておりますので参考になさって下さい。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
政府の働き方改革の議論について
2016年9月30日11:44 AM
政府内で一億総活躍社会実現の主要テーマの一つとして働き方改革の議論が盛んに行われています。
その目玉の一つが正社員と非正規社員の賃金格差を埋める同一労働同一賃金の実現です。安倍総理は、これで賃金格差を解消し非正規社員を無くすと言っていますが、ご存知のように非正規社員の賃金水準は正社員の6割弱~4割というレベルで、さらに、正社員が本人の能力ベースで昇給し担当職務の内容に直接リンクする賃金ではない職能給なのに対し、非正規社員は主として職務給ベースで本人の担当する単一職務の賃金であり、昇給があっても極く限られています。
正社員になれるかどうかも、毎年度の景気不景気によって就職率が大きく変わってしまうため、卒業年度において正社員になれなかった学生は非正規社員になるという日本独特の現象があります。さらに、卒業後の中途から正社員のコースに乗ることも大変難しい状況で、このあたりのところも社会の構造を改革していく必要があります。
話を戻しますが、同一労働同一賃金の実現は、賃金制度も異なり格差も非常に大きいだけに非常に難しい課題です。政府は、正社員と非正規社員のどんな待遇差が合理的でないかの事例を示すガイドラインをとりあえず年内に発表すると言っていますので、私共もできれば参考にしたいと思っています。
皆さんの企業では、どのように考えておられるでしょうか。
既に私共は、様々な企業のご要望に応じていろいろな仕組みや工夫を行い、正社員と非正規社員の賃金の制度の違いを別の方式や仕組みで結びつけ、賃金格差もいろいろな工夫で同一労働同一賃金に向けて取り組んでいます。少しでもお役に立てればと思いますので、何なりとご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
労働時間を有効に使うには、どうしたら良いか。
2016年9月14日11:49 AM
皆さんの職場では、労働時間を有効に使っていますか。
製造業の工場などでは、工場全体の生産性をもとに作業工程や作業時間を設定し労働時間を管理していますが、こうした職場以外では、なかなか労働時間の有効活用がなされていないのが現状のようです。
では、どうして労働時間を有効に使いきれないのでしょうか。
業種にかかわらず事務部門のホワイトカラーの職場などで共通して言えるのは、日常の長時間労働に慣れてしまっていて労働時間を有効活用して仕事をするという意識が希薄になっている傾向があることです。
皆さんの職場でも労働時間が有効に使われているか、一度、部門部署別にその実情を調べてみてはいかがでしょうか。業種や企業の状況よって実状は大きく異なりますが、おそらく半分以上の職場で改善が必要なのではないでしょうか。
労働時間を有効活用できない要因にはいろいろありますが、一つは、部門部署における要員の配置がいまだにマクロな管理で行われていて、要員要請が行われる都度に補充が積み重ねられ、部門部署ごとのミクロ管理が行われていないことが挙げられます。
これにより、多くの職場で労働の効率化が進まない状況が発生します。例えば、営業部門の営業活動の非効率性や建設業の作業現場における段取りや工程手順、資材搬入などの作業の非効率性などです。
これらの労働生産性をいかに引き上げるかは企業の大きな課題です。これには、部門部署単位のミクロ要員管理を導入するのと同時に、それぞれの職場の状況に合わせて労働生産性を向上するための仕組みを総合的に構築し実施する必要があります。特にこれからの労働人口の減少に対処していくためにも、これは大きな課題です。
当ホームページ内で要員管理や働き方、業務効率化、労働生産性などの関連する内容を掲載しておりますので、参考になさってください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
社員の働き方を変えていこう。
2016年8月31日11:12 AM
社員の働き方を変える必要があることは、3月15日のブログでお話しさせていただきました。
皆さんの職場の社員の働き方はどのくらい変わってきていますか。
厚生労働省では、働き方が一目でわかる数万社規模のデータベースを作り、近く誰でもインターネット上で閲覧できるようにして、女性の活躍がどのくらい進んでいるかとか、有給休暇の取得率や残業時間の削減がどのくらい進んでいるかなどがわかるように情報公開するそうです。
しかし、これらは企業とそこで働く社員が働き方を変えることができたという結果のデータであり、企業一社一社が働き方を変えることが実際にできて生まれた結果です。
長時間労働の短縮や有休休暇の取得率を増すことなども含めて、職場の全員で従来の働き方から変わっていくことを意識して実際に取り組まない限り、相変わらず一部の社員に仕事が集中し、労働過多の状況に陥ることになります。
社員の働き方を変えていくためには、社員の労働生産性や労働の効率化などに必要なプロセスや仕組みを示し、職場の人たち全員で変えていくことが必要です。
私どもはこれらの働き方を変えるプロセスや仕組みを整備作成する支援コンサルティングを行っています。同ホームページでもいろいろな記事を紹介していますので、ご参考になさってください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
皆さんの会社の人事制度は充分機能していますか。
2016年8月15日9:41 PM
皆さんの会社の人事制度は実際にどう活かされていますか。活かすどころか、逆に会社にとって大事な人事制度がお荷物になり邪魔になってしまっているなんてことになってはいないでしょうか。
人事制度は、会社が従業員に期待すること、従業員が会社に期待することの二つのことをつなげる大事な役割を担う仕組みです。それが、どうしていつの間にか充分機能しなくなってしまうのでしょうか。そのいくつかのチェックポイントを下記に挙げてみます。
1.人件費としての賃金制度は、しっかりと整備できていますか。
2.評価制度は、従業員のための制度になっていますか。
3.従業員の人材育成は進んでいますか。
4.育成した人材を充分に活かせる職場が作られていますか。
5.人材の確保のための採用活動はしっかり行われていますか。
6.社内の要員の配置はしっかり行われていますか。
7.女性従業員やエルダー社員のパワーを活用することができていますか。
8.非正規社員のこれからの活かし方のプランを検討されていますか。
上記に挙げたポイントをそのまま企業としての課題として悩まれている方も少なくないと思いますが、これらは制度の大事なポイントとなる仕組みに少し手を加えることで、それぞれが相互につながり、それぞれの機能が集約されてパワーを発揮するようになります。
どこから手をつければいいか、どうしたら良いのか悩まれている企業の皆さんは、現状のままにしておくのではなく、どうぞお気軽にご相談ください。当ホームページのコンサルティングサービスの欄にも多様に掲載しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
派遣社員の無期雇用化が増えてきています。
2016年7月31日5:44 PM
有期の派遣社員を契約期限のない無期雇用社員にする動きが広がっています。
昨年9月の派遣法の改正で派遣先企業の受け入れ期間の定めが機械設計やソフトウエア開発などの26の業務で廃止され、有期雇用の派遣社員は同一の職場で働ける期間が職種に関係なく3年間に統一されました。このため、有期の派遣社員に同一の職場で働いてもらうためには、無期雇用の社員にしなければならなくなっています。
専門的なエンジニアやIT関係などにかかる分野では、3年を超える勤務を望む企業も多く、派遣社員にとっても現在の仕事を望む人が多い状況もあって、無期雇用化にする企業が増えてきています。
一方で、技術系の特殊な専門分野のみならず、無期雇用化の流れは一般の事務系の分野にも広がっています。
本人にとっては現在の仕事から離れて新たな職場に移ることに抵抗があり、企業にとっては定着して仕事ができる人たちを少しでも確保する必要があり、いまの求人難を背景とした状況ともあいまって、事務部門の派遣社員についても無期雇用での採用を始めている企業も出てきています。
このような無期雇用化の流れがこれからどのように発展していくか。政府は、非正規社員の正規社員化が進んでいくことを期待していますが、実際に無期雇用化した社員をさらに技能アップの教育投資で戦力化していくことや限定正社員から正社員へと処遇の改善へと進めていく企業が増えてくるのはこれからだと思います。
いままでの派遣社員を臨時に使い勝手よく雇うという考え方は通用しなくなってきています。この派遣法改正における無期雇用化については多くの議論が行われましたが、このような流れを契機にして派遣社員の囲い込みとしてだけでなく、それぞれの企業がこれからの対応を考えて進めていってほしいと思っています。
関連事項を同ホームページ内に多数掲載しておりますので、ご参考になさってください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
これからの求人難の時代をどのように乗り越えるか。
2016年7月18日7:49 PM
これからの景気の変動にかかわらず、雇用においては人口の少子化を背景に求人難の時代が続いていくことが予想されます。この時代をどのように乗り越えていくかは、企業にとって重要な課題です。
そのためには、単一的な対策ではなく総合的に、しかも構造的な対策を構築することが必要です。単に長時間労働の短縮化とか、非正規社員の雇用対策とかいうことの前に従業員全員の働き方を変えていくことが必要です。
わが国の労働の生産性がOECD34ヶ国で20番目以下になっているのを見ても、いかに1時間あたりの労働生産性が低いかがわかります。この改善のためには働き方を変えるという掛け声やスローガンだけでは改善できません。
それでは、どのような対策が必要なのでしょうか。従業員一人ひとりの仕事のスピードを上げる新しい仕組みを入れるなどでスピードアップを図るだけではダメです。併せて業務の効率化や能率アップの施策を併行して継続的に行う必要があります。
さらに、管理職全員の意識改革が必要です。率先して仕事の仕方を改革改善していく意識改革と実行力ですが、これも単なる掛け声ではなく新しい対策と仕組みが伴います。
上記の働き方の改革のほかに人材の確保と人材育成の方法も根本的に変えていく必要があります。人材の確保には、これからは不足している人材を重点的に確保していくことと、そのために求人活動の方法や手段も変えていくことが必要になってきます。
また、社内の潜在的な人材の発掘、登用や非正規社員の正社員への取り込みなどの従来とは異なる取り組みが求められます。さらには、勤務時間や勤務形態などの柔軟な新しい発想への転換も必要です。
このほかにも多くの課題が山積しています。これらをどのように体系化し、どこから手をつけるか。当ホームページ内で関連事項を掲載しております。少しはお役に立てることもあるかもしれません。ご参考にしていただければ幸いです。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
雇用管理の形が動き始めています。
2016年6月29日5:16 PM
最近、勤務形態や働き方などの雇用管理が活発に変わり始めているように思います。
勤務形態についていえば、この4月から中央官庁の国家公務員のほとんどの勤務でフレックスタイムをスタートさせています。
一般の企業でもフレックスタイムは目に見えて増加しています。社員全員が同じように長時間労働を行うよりも勤務の時間を一定の範囲や条件で社員自身が設定することで、むしろ能率も上がり、私生活の面でのメリットもあり、企業にとっても予想された弊害も特に起きず、ほとんどの企業が採用して良かったといっています。
さらに、最近は在宅勤務を採用する企業も増えてきています。在宅勤務の日数を1週間で1日それも2~3時間ほどの出社で済ませるような企業もあるようです。在宅勤務は管理が難しいとか、社内コミュニケーションが不足するとか、企業情報や機密管理が難しいとか云われていますが、これらも一つ一つ工夫し新しい仕組みを行えば解決できますし、実施することで、企業にとっても社員にとっても大きなメリットが期待されます。
これには、私共も、在宅勤務形態を採用しやすい部門からスタートし、トライアルによって全体に展開させるなどの新しい仕組みを使ってお手伝いしています。
一方、正規社員と非正規社員の働き方も変えていかなければならない時代がきています。いまのような長時間労働ではなく、発想を変えて働き方を変えることで労働の生産性も向上し、社内全体の活性化にもつながります。
例えば、短時間労働の限定正社員制度が非正規社員の正社員化への受け皿になっているように、非正規社員の雇用管理に関連する労働法規が次々と改正されており、これらに対応することによって、正規社員と非正規社員の再編成への見直しが行われ、全体のトータルパワーアップの促進や人材確保の道に繋がっていくと思われます。
これから少しでも現状を変え、新しい一歩を踏み出す企業が増えていくことを期待しています。
同ホームページ内で雇用についての関連事項をいろいろ掲載しておりますので、ご参考になさってください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
職務給と職能給のそれぞれの功罪について
2016年6月14日9:40 AM
最近、職務給がいろいろ注目されてきています。
ご存じのように職能給制度は、すべての職種に共通の職務遂行能力(職能)要件を別に定め、それで評価し算定する制度で急速に普及しました。多くの企業で使われています。
職能給制度は、部門部署間にわたって人事異動がしやすく、能力開発や人材育成も共通の職能要件で全社で横断的に行うことができるなど多くの利点がありました。
しかし、一方において職能要件が具体性に欠け、基礎的な部分では機能し得ても職務上の具体的要件にまでには不十分で人材育成や能力開発にも限界がありました。このため、私共は職能要件をより具体的な技能レベルにまで追加し、さらに評価には能力評価に替えてコンピテンシー評価をもとに行動評価を行うなど、いろいろ新しい仕組みを作って補強してきました。
これに対し、職務給賃金制度は、上記の職能要件書に替えて担当の職務の達成に必要な技能を軸に職務記述書を作成し、それをもとに職務評価することで職務給を算定する制度で担当の職務と賃金がマッチした制度になっています。これにより、職務達成に必要な技術技能の能力アップに直接機能させることができ、一層職務の達成に役立つことが期待されます。このため、職務給制度が注目されてきています。
一方において、部門間にまたがる人事異動などで人材を広く活用できなくなるのではないかなどの意見がありますが、それは心配するほどのものではなく、職能給制度と同じように新しい仕組みを作り、職務給制度におけるデメリットを補強し、良い点を活かしていくことは充分可能です。
これからは、経営目標の達成にとっても、社員の一層の成長にとっても、職務給賃金制度の方が適する業種や部門が増えてくるように思います。例えば、部門では、専門の職種で技術部門や生産部門などが、業種では、専門能力を一層活かす必要のある新規事業や流通業各種サービス業などが予想されます。
また、今いろいろ議論されている正社員と非正規社員の格差是正も職務給制度で両者をつなげることで同一労働同一賃金の実現も行いやすくなります。
皆さんは、どのように思われますか。
当ホームページのコンサルティングサービスの欄で職能給と職務給の賃金制度や職能要件書や職務基準書、それによる評価制度のことなども掲載しておりますので、参考にしていただければ幸いです。
カテゴリー:賃金制度
ダイバーシティ組織を目指そう。
2016年6月1日8:45 AM
ダイバーシティ組織とは、多様な人材を積極的に取り入れて、その多様性を活かして経営環境の変化に迅速に対応し、企業の一層の発展と社員の成長を促す組織を言います。
経営環境は、既に大きく変化してきています。従って、このダイバーシティの組織に移行していかないとどのような企業も行き詰って経営が難しくなっています。そして、このような組織への移行のためには、企業の社員の働き方を変えていくことが必要です。
その一つが、現在行われている長時間労働からの脱皮です。ここから脱皮しないことには女性やシニア世代の活用のような柔軟な雇用形態の拡大に取り組むことは困難です。これには、益々国際化する中で、多くの国々の優秀な人材の活用も含まれます。
しかし、長時間労働からの脱皮には、労働生産性の向上が不可欠です。ただ、単に長時間労働を短縮しようとしても、さらに社員に過重な労働を強いることになってしまいます。労働生産性を向上させるには、さまざまな仕組みを構築することが必要です。その詳細については、当ホームページ内コンサルティングサービスの労働時間管理のページに掲載しておりますのでご覧ください。
私共は、さまざまな分野でこの取組みを行っています。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
私共は、人事考課をこうして人材育成に活かしています。
2016年5月16日9:24 AM
ほとんどの企業では、人事考課を処遇に反映するための制度として運用されていると思いますが、私共は、さらに人事考課を人材育成に活かす仕組みに工夫して運用しています。
一人ひとりの人事考課表を見ると、本人のどこが不足しているのか。それは、どこに原因があるのか。評価すべき特長はどこか。業績に貢献している部分はどこか。などがはっきりと見えてきます。
そこを足掛かりに、本人についての人材育成のプランを考えるのです。医者が検査等のデータから考えるのと同じで、本人の人事考課表をよく見ると、どこをどのようにしていったら良いのかがよくわかります。そのためには、いくつかの要点が必要です。
一つめは、人事考課を人材育成のために活かせるものに直すことが必要です。例えば、成績とか業績の評価項目の考課の内容が、能力要件や行動特性などの評価項目の考課内容と関連して読み取れるように考課表の構造や仕組みを直すことです。
二つめは、各人の人事考課表をどのように読み取るかの方法を学ぶことです。私共では、いくつかのトライアルの中で、具体的な読み取り方の研修等を行い指導しています。
三つめは、読み取った材料をどのように人材育成に活かすかです。そのためには、仕組みが必要です。読み取った材料を課題化して、本人の人材育成に役立てるプロセスを作り、それに沿って課題を改善するための活動を促進できるようにすることです。
この三つができれば、人事考課を人材育成に大いに活かすことができます。本来、人事考課は人材育成のために使うものなのです。
私共では、人事考課を上記のような要点のもとでのご利用をお勧めしており、多くの企業から評価をいただいております。なお、ホームページ内の「コンサルティングサービス」の欄でも、人事考課や人材育成についてご覧いただけます。ご参考にしていただけたら幸いです。
カテゴリー:評価制度
貴社の現在の賃金カーブの見直しをしてみませんか。
2016年5月1日2:27 PM
毎年度、初頭になると賃上げの問題や正規社員と非正規社員の格差是正などが盛んに議論されます。現状の格差を半分までにしたい等の意見にどう対処したらよいかの議論も必要ですが、企業としては、それぞれの賃金構造を見直してみる必要があると思います。
その理由としては、経営環境が大きく変化するのと同時に雇用状況も大きく変化していることです。少子化により若年層の人材が不足し、必要な人材の確保が困難になっています。一方で、高齢化により、雇用期間の延長も必至です。さらに、企業によっては、中堅職層のパワーアップがこれから一層必要であるにもかかわらず、人材育成がうまく進まず、チャレンジ力も足りないことにより、賃金水準がやや低位で推移している状況があります。
このような状況から、有限な人件費を有効に活かすために、現状の賃金構造を見直すことが必須と考えます。
まだ、あまり考えておられない方は、一度、若年層から高齢層に至る従業員全員の賃金カーブを描いてみて、どのような賃金構造にするべきかを考えられてみてはいかがでしょうか。
賃金や雇用関係の事柄も同ホームページに掲載しております。また、データ不足なことやわかりづらいところなどがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリー:賃金制度
人材育成には、しっかりした計画が必要です。
2016年4月15日8:35 AM
人材育成は、どの企業でも益々重要な課題になっていますが、無計画な人材育成は非常に危険です。
企業によって活動している事業が異なるので、将来に備えて求められる人材のタイプもそれぞれの企業によって違いますが、いま現在、どういう人材が不足しているのか。将来、どのような人材が必要なのかをよく考えて人材育成をしていかないと後で大きな誤算を生じかねません。
無計画な人材育成によって、必要な人材の確保につながらないことが多くの企業で発生しています。
皆さんの企業ではいかがでしょうか。
人材育成は非常に重要ですが、それに見合う人材活用の場をクリエイトできないと、折角、人材育成に注力しても、その努力が実らずに、逆に人材を手放す破目になり、定着率を下げる結果となってしまいます。人材育成は、人材の育成をするのと同時に、何のために行うのか、しっかりした計画ができていなければ、その人材育成を活かすことができないのです。
さらに、社内における、それぞれの役割や職務に相応した人員配置が行われているかも重要な課題です。社員の中には、単一の同じ職務に従事することを希望する者もいれば、新しい高度な業務にチャレンジすることに適した人材もいます。それにもかかわらず、単一業務に多能化した人材を配置したり、ある部署では人員が不足しているのに、他の部署では過剰人員であったりと多くの職場でミスマッチな人員配置が行われていることが少なくありません。こうした結果、社内に埋没してしまっている人材がいるのではないでしょうか。
これからは、先を見据えたしっかりとした計画をもとに人材育成を行うこと。それと同時に、部門部署ごとのミクロの要員管理と企業全体のマクロの要員管理が必要になっています。要員管理についても、ホームページ内のコンサルティングサービスの欄でご確認ください。
カテゴリー:人材育成
残業時間80時間で立ち入り調査
2016年4月1日9:00 AM
政府は、長時間労働に歯止めをかけるため、1ヶ月の残業時間が80時間でも労働基準監督署の立ち入り調査を行うといっています。いままで1ヶ月の残業が100時間に達した場合に行う立ち入り調査を月80時間に引き下げる方針です。
長時間労働は、仕事と子育ての両立を困難にし、子を持つ女性の活躍を阻む原因になっており、長時間労働を少しでも減らすことで子育てをしている女性が働きやすい環境を促進する狙いです。
このため、立ち入り調査の対象となるのは、80時間を超える残業をしている従業員が一人でもいると疑われる企業で、従業員の通報などを通じ重点的に調査が行われます。
また、調査の結果、違法の残業代の未払いなどがあれば、是正指導し、改善できない企業については、いままで以上に罰則が強化されます。
平成15年度の労働力調査によると全国の常勤労働者は約5000万人で、このうち100時間を超える残業をしている人は、少なくとも約110万人はいるといわれています。
今回、80時間を超える人は約300万人と予想されており、今回の立ち入り調査の対象となる労働者は3倍近い人数になると思われます。
全国の労基署による平成14年の立ち入り調査は約135万件で、このうちその7割が何らかの法違反になっています。労基法では36協定を結べば残業ができますが、それでも厚労省は月45時間までにするように求めています。しかし、特別条項付の36協定を結べば45時間以上の残業になり、残業時間が長くなる原因となっています。
この残業時間の削減と長時間労働の短縮は、いずれにしても、企業にとって、社会全体にとっても大きな課題です。これをなんとか克服して新しい働き方を工夫していく必要があります。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
これからは、仕事の働き方を変えていくことが必要になってきています。
2016年3月15日11:59 AM
前回のブログでは、正規と非正規社員の格差是正について話をさせていただきましたが、それに関連して、正規社員と非正規社員とに、それぞれ大きな課題があると思っています。
一つめの課題は、正規社員が、なお働き過ぎだということです。これを改善していかないことには、どうにもならないと思います。世界的にみても、日本の労働者は働き過ぎで、時間あたりの生産性について無関心だと云われています。
人口減少が加速する現在、女性や高齢者、さらに外国の方などの幅の広い人材の活用が求められるときに、限られた時間で労働生産性の成果を引き出す仕組みが必要です。この働き方の改革を進められないようでは、企業の成長、さらには社会全体の成長も進まないように思います。
もう一つの課題は、非正規社員の収入増の必要です。今までは、安い賃金でコスト低減のために非正規社員を増やしてきましたが、これからも同じような考え方では成立しなくなってきています。働く場を求める非正規社員の中の多くの有能な人たちを積極的に活かすための対策を立てていくことが必要です。
社会全体からみても、非正規雇用の社員は雇用全体の4割に迫っています。このような状態をどのように考えるか。いろいろな考え方がありますが、非正規社員をどのように処遇し、どのように位置づけて積極的に活用するための施策を講じていくかが、企業にとっても、社会全体にとっても重要な課題であると思い、私共もいろいろ工夫し取り組んでいます。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
最近の投稿
- リテンションマネジメントについて
- 思いもよらずハラスメントと訴えられてしまったら
- 組織における社員のキャリアパスについて
- 組織開発に有効なデリバラブルについて
- 人事制度の見直しについて
- 育児介護休業法等の改正について
- 企業の熱中症対策義務化について
- 人事評価制度のトレンドについて
- 新入社員の早期離職の防止について
- 若手社員の早期戦力化について
カテゴリー
月別アーカイブ
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)