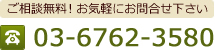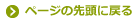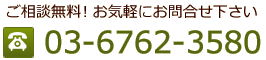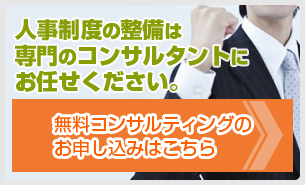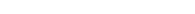株式会社マックブレイントップページ > 人事コンサルティングブログ
人事コンサルティングブログ
要員管理は、しっかりできていますか。
2015年10月15日2:04 PM
少子高齢化の時代に入り、従業員全員の要員管理は充分に整備されていますか。
企業全体でいつの間にか過剰人員になっていたり、一部の部署では人員が不足しているのに全体では過剰人員になっていることが少なくありません。
適正人員規模を維持するには、総人件費によるマクロ管理の要員管理では充分な管理はできません。やはり、部門部署別による営業・管理・製造・技術開発など全部署における所謂ミクロ管理が必要です。
事業規模の推移やそれに必要な要員規模で推定し、年度ごとの要員査定をするだけでは概算によるおおよその要員数の把握しかできず、各部門部署の要員ニーズやそれによる増減の把握まで正確に捉えることは不可能ですが、ミクロの要員管理を行うことにより、企業内の全部署の要員ニーズを掴むことで、各部署の適正人員規模の実現を達成することができます
さらには、職種ごとに各部署の業務の効率化や必要な人材育成と能力開発もこの要員管理をもとに具体的に促進することが可能になります。また、社内における潜在的な人材や社員一人ひとりを有効に活動させるための体制もでき、全従業員の活性化にもつながります。
このミクロ管理は、これからの求人難の時代に必要不可欠な人事制度であると思います。しかし、一方で複雑で難しいものと考えられがちです。
私共は、そうした要員管理の仕組みを有効に機動的に活用できるように可能な限りシンプルに整備、構築することに努めております。詳細は当ホームページ業務項目欄にアクセスのうえ、ご覧ください。
カテゴリー:要員管理
残業を減らし、社員の人材力を高めよう。
2015年9月30日10:33 AM
どうしたら残業を減らすことができるのか、多くの企業で悩まれていることと思います。
残業を減らしたいが、実際には決心して行動に移すことができていない企業が多いのではないでしょうか。
では、残業を減らすためには、どうしたらいいのか。
まず、仕事の工程を作り替えることが必要です。それで時間が不足しているようであれば不必要な仕事の削除をする。仕事のスピードをあげる。そのための仕組みを導入することです。
さらに、労働時間をもっと上手に使うために週単位や月単位での変形労働時間制を導入することで仕事の繁忙度に合わせて時間を調整するなど、自社の特性に合わせた形態の勤務時間に変えることです。
短納期の注文を受ける下請企業に関しては、発注企業との徹底した話し合いが必要になってくるので、その交渉は非常に難しいことでしょう。ただ、それを打開することができれば将来が見えてきます。
残業を減らすことができれば、社員の生活にゆとりが生まれます。その時間を使って心身のリフレッシュや趣味に興じるなどの潤いができるので、それは確実に仕事に反映されます。さらに、人材力を高めることに時間を振り向けることによって、社員一人ひとりの生産性、収益性は、より向上します。
残業を減らすことに成功した企業は、こうして社員の仕事の生産性や収益性を向上させています。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
労働者派遣法が改正されました。
2015年9月18日6:57 PM
派遣労働者の企業への派遣受け入れ期間を事実上なくす労働者派遣法の改正が国会で可決されました。
これまでの派遣法では、研究開発や通訳などの26の専門業務を除き、企業が派遣労働者を受け入れる期間を最長3年に限定していましたが、すべての企業の全業務で派遣労働者を受け入れる期間の上限がなくなります。但し、同じ派遣労働者を受け入れるには、3年ごとに業務に従事する「課」を変えなければ、同じ事業場では働けなくなります。
これには、いろいろな意見があります。
企業側からすれば、3年ごとに人を入れ替えれば、同じ業務で3年の限定がなく派遣労働者を受け入れることができるので良いという意見もあれば、一方で同じ人を受け入れられないので不便だという意見もあります。
派遣される労働者の側からすると、同じ業務に従事できる期間は3年で、それを超えると同じ事業場で働くには、新しい「課」の業務に移らなければいけないので、大変不便さを感じる人が多いのではないかと思います。
しかし、逆にこのことが派遣労働者の業務の範囲を広げ、単一の業務に従事するだけでなく、いろいろな業務を経験することにより正社員への道につながるのであれば、派遣労働者にとってプラスになるのではないかと思います。
ただ、それには派遣労働者の自覚や努力が必要ですが、行政や企業も派遣労働者を大事な人材として支援していく姿勢が今以上に必要だと思います。
今までと異なり、労働環境は著しく変化します。これからは、どの企業でも人材を育成し確保していくことが、より一層重要な課題になってきています。派遣労働者を安易に使うという考え方を大きく変えて、いかに確保し、もっと活躍してもらう場を広げていくかを考えることが必要だと思います。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
長時間労働をもっと減らそう。
2015年8月31日9:46 AM
多くの企業で終身雇用や年功序列などは減ってきてはいますが、依然として古い体質が残っているのは長時間労働です。
日本の年間総労働時間は、1765時間と年々減ってきていますが、これはパートなどの非正規雇用者の労働時間を加えているからで、正規雇用者に限れば相変わらず年間2000時間を超える状況で、これをさらにホワイトカラーの正社員だけに絞るとさらに長時間の労働になっています。
このため、1時間あたりの労働生産性を比較するとアメリカやドイツとは4~5割程低いレベルでフランスや韓国などよりも低く、先進国の中では低い層にランクされています。
そろそろ、もっと新しい知恵や工夫を動員して労働生産性を引き上げて長時間労働から脱皮していかないとこれからの競争に勝ち残れなくなってきます。
特に中小企業では難しいと思われがちですが、考え方や発想を変えて取り組めば不可能ではありません。短時間労働でも売り上げや利益が減ってしまうのではなく、逆に増加して発展している企業をたくさん見てきました。
それらの企業は、長時間労働による疲労や弊害を減らして従業員の健康を増進し、ワークライフバランスを考えることで新たな知恵や独創性を向上させて、それを企業の成長と発展に寄与することに成功しています。
このためには、それぞれの仕事の仕方や働き方を基本から見直し改善することに逆転の発想で取り組むことが必要です。現状のままの長時間労働を続けていく限り、従業員のやる気や人材育成も中々進まず、さらに求人活動も困難になってきます。
私共は、長時間労働対策も主要なテーマとして取り組んでいます。
ご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
人事制度の見直しや作り方など、どのようなことでもお応えします。
2015年8月16日3:12 PM
今の人事制度を少し手直ししたいとか、新しい制度に作り直したいとか、どこをどのようにしていけばよいのか、などで悩んで決められないでいる企業の皆さんが多いのではないかと思います。
どんなことでもお気軽にご相談ください。どのようなことでもお話できますし、そこからきっとヒントが得られると思います。こちらのホームページでも、できるだけわかりやすく制度作成の手順やポイントなどを紹介していますので、ご覧いだだければ幸いです。
現在運用中の人事制度についても、できるだけ活かしながら要所を重点的に補強する方法があります。差支えない範疇で現状を伺えれば、課題や改善点などをアドバイスさせていただくこともできます。
私共は、企業の皆さんご自身で人事制度を一つずつ作っていくお手伝いもしています。ご自身で制度を作ることができるのであれば、その効果は倍増するからです。
例えば、社内でプロジェクトチームを作って適当なメンバーを集め、テーマを選び、スケジュールを立て、制度整備を計画します。それに、私共がプロセス中に必要なアドバイスやデータ、ツールを提供してサポートします。そうして制度の作成を進めていくうちに、その作成の過程を通じて、参加メンバーらの能力向上や人材育成に役立つメリットが生まれます。そして、そこで培った能力やノウハウは、人事制度の整備以外にも活用することができるようになり、より広く、いろいろな課題に取り組むことができるようになるのです。
いずれにしても、考えておられることを何らかの形で行動に移すことが大事なのではないでしょうか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
人事管理や人事制度の一つを変えることで大きな変革が期待できます。
2015年7月31日3:15 PM
人事管理や人事制度を一度に全部にわたって変えなくても、できるところから一つずつでも変えることで大きな変革が期待できます。人事管理や人事制度は、従業員に直接つながることで経営管理と表裏一体となるものだけに、人事制度の一部だけでも、これを直すことで大きな変化が生まれます。
例えば、毎月支払われる賃金給料はどうでしょうか。毎月のことでマンネリ化してはいませんか。相変わらず旧態依然の制度や内容でよいのでしょうか。
そこに新しい仕組みやインセンティブを加えることによって、従業員に大きな期待と意欲を与えることは間違いないですし、賃金管理に多くの仕組みができているのなら、従業員にわかりやすい仕組みに変えることでも、現状は変わるでしょう。
評価制度でも同じことが言えます。それぞれの企業の特性や実態に沿ってわかりやすく、行いやすく、しかも評価制度によって従業員と企業の絆や連帯感を培い、仕事への励みや意欲につながるものにすることが大切です。これも他社の真似や古い内容のものを依然そのまま使っていませんか。
こうして見てみると、他にも沢山あるのではないでしょうか。
思いったったら吉日。少しずつでも、制度を見直し整備していくことが必要です。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
派遣社員などの非正規社員に対する考え方を変える時期がきています。
2015年7月15日5:21 PM
今まで多くの企業で非正規社員を仕事の忙しさに合わせて都合よく使っていた状態が続いていましたが、ここへ来て、その状態が大きく変わろうとしています。
その大きな原因は、人口の少子化を背景に若い労働力人口が減少してきていることと雇用人口に占める非正規の人たちの割合が40%を超える状態になり、正社員との賃金格差が著しく大きいことで、いよいよ社会問題としての深刻な影響が発生してきているためです。
非正規の人たちの雇用は、いつでも不安定な状態ですし、最近の景気の上向きの状態の中で非正規の人たちのその人材の取り囲みが始まっています。
政府も非正規の労働者の雇用の安定化を考え始めました。最近の労働者派遣法の改正もその一つの表れだと思います。派遣法の改正が成立すると、専門的業務も含めてどの業務についている人でも3年が経過する10月以降は同じ業務で3年を経過している場合、違法派遣とみなされて派遣先が派遣社員を直接雇用する契約が自動で成立します。
さらに、非正規社員を正社員に転換したり、処遇の改善を進めたりする企業へ助成金の増額や拡大を行うことで、非正規社員の正社員化を促進し、雇用の増加や安定を図ろうとしています。
ご存じのように非正規の社員の契約が通算して5年を超える場合は、本人の希望により無期雇用に転換されるようになります。
非正規社員に対する考え方をここで変える必要があります。企業の発展と同時に雇用の安定を図るためには、非正規の社員の人材確保や人材育成、さらに能力向上と成長を期待する考え方が重要になってきています。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
どこの企業も人材確保が益々重要な課題となっています。
2015年7月2日1:48 PM
来年春の就職活動が始まり、学生のみなさんは、あちらこちらと忙しい状況と思います。そうした中で、企業は少しでも良い人材を採用しようとしますが、それがさらに難しくなってきているようです。
この状況はこれからも続くと予想されます。
企業側は採用計画やその方法を見直す必要があります。従来通りの方法では、毎年採用できる人数も減少しますので、どういった人材を採用するかをも含めて方法の見直しは必須です。
将来のことをマクロの要員予想で採用すべき職種と人数を決めるような方法では、益々ジリ貧になりかねません。社内のニーズをミクロでピンポイントで把握し、ニーズにマッチした人材を獲得する手段をもっと工夫することが必要です。新卒の学生を採用することだけが人材確保ではありませんので、中途の採用での人材確保も重要といえます。
しかし、これも外部から人材を取る方ばかりに注力していると、そのうちに折角の社内の優秀な人材を逆に取られてしまう恐れがあります。社内の人材をいかに確保するかも大事ですので、社員の満足度調査をするなどしてみてはいかがでしょうか。経営者や管理職が知らなかった状況が見えてくるかも知れませんし、そうした企業は少なくありません。
社員の働く満足度が低い状況であれば、そのような状況を放置することはできませんし、適正な要員規模を図ることもできないでしょう。
人材確保は、外から取ることばかりではありませんので、社内にも目を向け、埋没している人材を引き上げることも方法です。正社員だけでなく契約社員やスタッフ社員の中にも優秀でやる気のある人材がいるはずです。多くの企業で、既にそうした非正規社員の正社員化を始めています。
さらに言えば、定年後の再雇用者の活用も方法の一つです。
少子高齢化が進行する中で、経験豊富であり、さらに発想が豊かでやる気のある人材がいれば、そうした人たちを活用することです。そのためには、定年までの現役社員と定年後のエルダー社員との働き分けと住み分けができる再雇用管理の仕組みが重要です。
しかし、こうした仕組みは、しっかりと構築されていないと台無しになってしまいますので、その作成には注意が必要です。私共は、長年、多くの企業で人材確保や人材育成の仕組みの構築を行っています。お気軽にご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
非正規社員から正規社員への登用を考えよう。
2015年6月17日8:52 AM
既にご存じと思いますが、平成25年4月以降の通算で5年を超える期間で同一の企業に雇用された有期雇用労働者は、本人が希望すれば無期の雇用契約に転換されるようになります。
この機会に皆さんの企業でも長年、非正規社員として働いておられる人たちの中から、これからも頑張ってもらえる人たちを正社員に登用することを積極的に考えてみられてはいかがでしょうか。
見逃しがしがちですが、日頃身近で働いておられる非正規社員の人たちをよく見ると、きっと良い人材がいるはずです。その中から少しずつでも正社員として人材の確保をされると良いと思います。
これからは人が不足してきます。非正規社員の人たちの中には、今の場所で今の仕事を続けたいと考える人たちがいると思います。いろいろ希望を聞きながら、企業側もいろいろな条件を設けるなどして徐々に進められみてはいかがでしょうか。
例えば、初めから正社員の働きぶりや能力のレベルを全て期待するわけにはいかないので、仕事のキャリアを積んで成長していくごとに段階を踏んで正社員と同等の処遇条件にまで上げていく仕組みを作ります。当然、正社員は働きに応じて昇格していきますので、非正規社員から正規社員に登用されれば昇格も、またその逆もあるという考えです。
現状のままの正社員と非正規社員の区分から、新しい労働秩序というか社会ルールが生まれてくると思うのですが、その先駆けとして、どういう企業社会が到来すればよいか、皆さんもいろいろ模索する必要があるのではないでしょうか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
いろいろな企業で総合職の社員を作り出すことで苦労しています。
2015年5月31日5:22 PM
どの企業でも、上司の命令を一つ一つ覚えていて仕事をしっかりやる社員はいると思いますが、職場の状況を総合的に判断して自分から率先して課題や難しい案件に取り組み、解決しようとする社員は、なかなかいないのではないでしょうか。
ある企業で総合職を育てるべく、中堅職の社員の中から見込みのある社員を選抜して2~3年かけて、いろいろな方法で研修指導を行っています。
しかし、これなら役に立ってくれる、と送り出しても、いざ配属されると萎縮して行き詰ってしまうことが多いのです。どうも、配属先の上司や周囲の圧力や期待などに負けてしまうことが主な要因のようです。
上司の中には、しっかりと総合職を使い切れる人も勿論いますが、ほとんどの上司が今までの職場秩序の感覚から変わることが出来ずに総合職を活かせません。中には、総合職は職務が明確でないので使いにくいとか、大変な仕事をさせれるのに将来のことが約束されていないので不憫だとかの声も聞こえてきます。
しかし、このような状況でも、総合職になろうとする若者たちはチャレンジ意欲旺盛で、多くの人たちが志願してきます。その中から毎年1割を総合職とすることを目標に企業も本人たちも努力しています。
これらの人たちが、将来いかなる環境にもめげずに頑張ってくれることを願って、これからも指導を続けていくつもりです。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
派遣労働者の若い人たちほど「できれば正社員として働きたい」と考えています。
2015年5月16日4:27 PM
東京都がまとめた最近の調査によると、10~20代の人たちの60%近くが正社員を希望しており、30~50代でも40%以上が正社員になることを希望しています。一方で、60歳以上になると派遣の仕事をそのまま続けていきたいと考える人が多いようです。
若い人たちにとっては、これからのことを考えると雇用の安定が大事です。やる気があり、健康で能力もあって頑張ろうとしている人たちに正社員への道が、もっと広がっていってほしいと思います。
企業側にとっても、有為な若い人たちは大事な人材です。これらの若い人たちには門戸を広げて積極的に正社員化しチャレンジする機会を与えていくことが望まれます。
派遣労働者の派遣期間の制限を無くす労働者派遣法の改正案が、この国会で審議入りしました。
野党は、生涯派遣で低賃金の派遣社員が増えると反対しています。一方、与党は、働く人たちのそれぞれの選択を広げる環境を整備し、同時に派遣会社に正社員化を支援するキャリア相談を義務付け、派遣労働の固定化を防ぐ措置を強化すると言っています。
どちらが本当で正論なのでしょうか。
労働者派遣法改正案を巡って「10.1問題」への懸念があるようです。
現行法は、今年10月1日に3年を迎えるので雇い止めや労働紛争が起こりかねないという問題があり、この10月には、労働契約申込みなしの制度が施行されます。
総務省の労働力調査(今年1~3月期)によると、派遣労働者は120万人で前年同期に比べ4万人と増え続けている状態です。
こうした状況に対応すべく、私共は非正規の人たちの正社員化へのいろいろな仕組みや制度を作っています。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
非正規の有期雇用労働者が無期雇用に転換されます。
2015年5月2日4:30 PM
契約社員などの有期雇用の労働者が日本の雇用人口の全体の40%を超える状態ですが、平成30年4月には、通算で5年を超える期間に同一企業で雇用されている労働者が希望すれば、その申込みをした翌年度から無期雇用に転換されます。
これは、労働市場において大きな変革になると思います。これを契機として、正規雇用と非正規雇用の格差があまりにも大きくなっている社会構造が少しづつ是正へと向かい、非正規雇用の労働者の雇用が安定化し、労働市場が活性化されれば、日本の社会全体にとって望ましいことだと思います。
そこで、この無期雇用化によって、企業側も労働者側も、どのように対応していくかが大事ですが、皆さんの企業では、どのように対処していますか。
企業の側からすると、この有期雇用の無期雇用化を積極的に捉えて、寧ろ、これを契機として自社の非正規社員をより一層戦力化していってほしいと思います。
担当の職務を長年にわたり貢献している有期雇用の社員が無期雇用に転換されることによって、安定した雇用で一層業務に努められるようになれば、企業にとって確実にプラスになります。彼らが、さらに段階を踏んで能力の向上や成長をとげ、さらに職務の充実や拡大を図ることができれば、企業にとっては、大きな人材の確保になります。
有期雇用の人たちが希望し申し込まなければ、無期雇用への転換はされませんので、この機会に積極的に企業に申し出て新しい挑戦に取り組んでほしいと思います。
多くの企業で、この無期雇用化に伴い、勤務地や職務の限定、さらには短時間勤務などを組み合わせて、今までと同じように従事できる制度を作り対応しようとしています。
企業と非正規の人たちの両者が、この無期雇用化への転機を上手に活かしてほしいと思います。
何かわからないことがあれば、なんでもご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
勤務時間を朝型にシフトする動きが広がっています。
2015年4月15日3:53 PM
多くの企業で、従業員が長時間労働に慣れてしまっていることにより、会社の中に一旦入ると日中の所定労働時間を有効に使う感覚が低下し、夕方から2~3時間の残業が普通化している状態です。
企業によっては、短い納期を恒常的に強いられているなど、どうしても発生する残業が少なくありませんが、多くの企業において、残業をしないでも、もっと工夫をすることで仕事の能率を上げることが業績アップや従業員自身の成長促進など、経営上において良いのですが、一向に残業は減らず、むしろ増え続けている傾向にあります。
そこで、一部の企業で、夕方からの残業を減らすために、一定の時刻で残業を禁止するだけでなく、朝の勤務時間を1~2時間ほど早めることを始めています。早起きは三文の徳と言われているように、多くのメリットがあります。健康にも良いし、朝方のほうが頭も回り、能率も上がり、良いアイディアも生まれます。
さらに、その分、夕方の帰社時刻を早めることによって「work well」から「live well」と帰社後の余暇時間が増え、生活のエンジョイや家庭をもたれる女性にとっては育児や家事などに余裕ができ、女性の職場での一層の活躍が促進されます。
日本の長時間労働に慣れきっている状態は、先進国としては非常に低いレベルにあり、早急な脱却が求められています。そのためには、企業が、働く従業員の「労働時間をいかに有効に使うか」の課題に向かって、もっと努力することが必要です。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
最近の就職活動は、かなり変わってきています。
2015年3月30日8:06 PM
来年春の就職活動が本格的に始まりました。しかし、その就職活動が、景気の上向きとこれからの人手不足の影響を受けてかなり変わってきています。
まず、就職先の企業の選択ですが企業の規模や高収入という選択基準だけでなく、自分の能力を活かした活動ができ、かつ、企業の発展と合わせて自分も成長できる職場を期待するように少しずつ変わってきています。
また、依然として長時間の労働で残業が多い状態の企業が多く存在しますが、最近は、そのような企業ではなく、社員の自立と創造や工夫を促し、能力や能率をあげることで長時間労働の短縮化や残業の削減ができるような企業を求めるようになってきていると思います。
先進国の中で一番低い労働環境から脱却し、社員の創造性を促し、活力ある職場形成が進んでほしいと思います。このようなことは、一部の企業で新しい考え方が進み具体化してきていますが、一方で多くの中小企業で長時間労働の状況が続き、そこから脱却できない状態にありますが、企業と従業員が協力し合って仕事の仕方を変えることや新しい工夫や創造で現状を打開してほしいと思います。
もう一つ、就職活動で今までよりもさらに重視されてきているのは勤務地の選択です。これは、老老介護の構造が一層増してきていることが原因の一つですが、都市集中型から地方創生で地域貢献を重視する学生が増えてきているようで、これも良い傾向の一つだと思います。
これらの就職活動の最近の傾向を見ると企業のさらに新しい発想で新しい活力ある職場作りが必要だと思います。入社して3年もたてば新卒の3人に1人が退職する時代です。新しい発想で採用計画を練り直し、魅力ある職場作りに本腰を入れていかないと求人難の時代に向かって乗り切れないのではないでしょうか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
研修指導をしていて考えること。
2015年3月15日7:33 PM
さまざまな研修会の指導をしていていろいろなことを考えさせられます。
私共は、多くの企業からご依頼いただいて、様々なテーマの研修指導を行っています。
テーマによって、それぞれの企業の特徴やご要望、ご希望などをまとめて指導プロセスを決めています。
研修で使用する資料は、以前に使用したものを使うのではなく、その都度違う研修テーマと研修を受ける人たちにフィットするように新たに作成します。一つ一つの研修によって、その研修を受ける人たちが今、何を求めているのか、仕事をしていて何が不足しているのか、どこを補強すべきかなどが違うからです。
研修指導を行う際は、その研修でどの程度の効果を達成させるかの目標を幾つか設定して臨みます。そこでは、通常の教室形式で講義するような方法はあまりしません。講義と講義の間にケーススタディを随所に入れてそれに取り組んでもらい、各人に発表してもらいます。そこで、即座にコメント、アドバイスし、時には双方向で、あるいは全体の討議で、その討議を深めるやり方で、多くを取り入れて進めていきます。
また、役員や上司の方々にも可能な限り参加してもらい、3方向での研修も行います。それにより、上司の方々の考えも、研修を受ける人たちの考えもオープンになり、そのプロセスの中で多くのことを学びとることができます。
要は、研修は一方通行で講義を聴かせるだけでは殆ど効果は期待できません。テクニカルの研修であればそれで済みますが、上述の現在の仕事の補強や活動の改善といったようなテーマの場合、ただ講義を聴いているだけの研修では職場での実際の行動の変化にまで至らないのです。
一般に外部で行われている研修会も私共も講師としてお引き受けしていますが、その場合は、特定の企業内の課題や目的ではなく、共通したテーマで行われるものなので、根っこの土台が違います。
さらに、企業内での研修は、継続して定期的に行うことが大事です。例えば、上期、下期の年2回を2~3年続けてシリーズ化するなど、本当に仕事に役立つ効果を期待するためには必要なことであると思います。それでも不足している人には個別にマンツーマンのフォロー指導を行っています。
こうして指導していくことは大変なことですが、その結果、効果は必ず表れます。そのときは報われた思いになります。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
今年もまた、新入社員を迎え入れる時期がきます。
2015年2月28日3:57 PM
この4月に新入社員をどのように迎え入れますか。
新入社員の採用には苦労されていると思います。
採用には、戦略と戦術が必要です。
まず、戦略に大事なのは選考基準です。どのような人材をどのように選考するかの方法手段です。いずれも間違えているところが結構多いようです。この時期になってしまってから、その部分を指摘しても遅いので、次はその新入社員をどのようにして迎え入れるかです。
ここで大事なことはその迎え方で、従来通りの方法でマンネリ化しているところが目立ちます。ここは最初が肝心で、教えるところは教えることが必要ですが、あまり気にせず行われているように思います。
最後に、新入社員のフォローができていないことです。配属した後、部署の上司まかせでは、とても足りません。その証拠に、入社2~3年程で他への転出者が急に増えてきます。折角、採用したのに勿体ないことになります。やはり、最初の上司のところで大きな差が生じてきますので、その対策とフォローが必要です。
皆さんの会社では、新入社員をしっかりと育てていますか?
毎年4月が近くなるとこのようなことが気になっています。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
労働時間をもっと有効に使おう。
2015年2月15日5:01 PM
1日8時間勤務の労働基準法の規定は70年ほど前の1947年に施行され、それ以来、この労働時間が続いています。しかし、この労働時間の使い方がどうかというと、どちらの企業でもあまり能率的に使われていません。
労働者が1時間に生み出す価値を示す労働生産性は先進7カ国のレベルでみると日本は40ドルでもっとも低く、アメリカ、ドイツ、フランスに比較すると3割以上も低い状態です。これには、いろいろな原因がありますが、日本では週50時間以上働く人たちが、労働人口の30%以上を占めるためと云われています。
一方において、まだどちらの企業でも残業が多い状態ですが、これを減らすためには、直接的に残業を抑制する手段をとるのではなく、社員一人ひとりの1時間あたりの生産性を引き上げる策を講じることが大事です。
労働時間対策となると残業管理や勤務形態の話になりがちですが、本来は、この1時間あたりの生産性を向上させる議論をすることが大事です。職場で活躍している社員ほど時間の不足を訴えることが多く見受けられますが、自分の労働時間とパワーを上手に使えるようになることで時間の余裕も生まれ、良い仕事を能率的に行うように変えていくことができます。
このためには、もちろん労働時間の総合対策が必要ですが、これに加えて、社員一人ひとりが労働時間を有効に活かして仕事をする自立した動きを活発にしていく仕組みを作ることが必要です。
皆さんの会社ではどのようにされていますか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
管理職の能力向上は、大事な課題です。
2015年1月31日7:38 PM
どの企業でも主要な事業計画をもとに経営戦略を重視し経営を行っていますが、管理職の管理能力の向上には、あまり目が向けられずにきました。そうした中、最近また、管理職の能力研修が盛んになって行われています。
管理職の能力の差は組織における最も重要な機能の差であり、企業の経営成績に大きく影響します。みなさんの会社の職場では、どうでしょうか。
部門部署に多く課題がそのままで解決できていないとか、業務の優先順位で役割機能が充分に発揮できていない、業務の分担が適切にできていない、マンネリ化が進みモラールも低下してしまっているなどです。
さらに挙げれば、ムダな仕事が多く仕事の能率も充分に上がっていない、部下をフルに活かすことができない、部下の人材育成が進まないなど。
私共は、これらの研修指導を行うと同時に管理職のみなさんが大事な管理業務を適切に実行していくために必要な仕組み作りにも取り組んでいます。
まずは、ご相談ください。
カテゴリー:人材育成
今年は労働法規の見直しの動きが続きそうです。
2015年1月14日9:23 AM
新年も私共のホームページへ、そしてブログを早速お読みいただいてありがとうございます。
今年は新年早々から労働法規の見直しの動きが活発に続きそうです。
例のホワイトカラーエグゼンプションの議論で厚生労働省は専門職の条件として年収1075万円以上の専門職に限り、週40時間の労働規制を外す制度をまとめたそうです。
しかし、これは極く限られた業種や企業において特殊な職種に限られたものです。
それよりも、中小企業や小規模企業にも広く労法規の恩恵が及ぶような改正が進んでほしいと思います。
例えば、人手不足の企業と過剰人員の企業間で相互に雇用人員を異動できる制度や正規社員と非正規社員の格差を縮小するためにその間の中間層を増やす社会作りも必要です。また、益々人口の老齢化が進むので老介護がしやすい労働環境作りなど、もっと介護休業や育児休業を取りやすくすることも必要です。
そのほか、国家公務員や大企業における女性登用よりも一般の職場での社会進出を促進する環境作りや男女の雇用均等の促進、女性社員の復職支援制度作りも大事です。
さらに、能力ある中高齢者をもっと活用促進する施策も労働人口が減少する中で重要なことですし、長時間の労働を減らすための短時間労働正社員を増やす制度、有給休暇をもっと取りやすい制度、フレックスタイムなどの変形労働時間制をもっと奨励するなど、列挙すれば、まだまだあるように思います。
皆さんは、どう思われますか。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
今年一年、有難うございました。
2014年12月31日4:10 PM
私共のホームぺージやブログをご覧いただきました皆さまには、今年一年、有難うございました。
私共が実際に仕事を通じて体験したことや見たこと、考えたことをもとにブログを書いてまいりましたが、読みづらく、わかりにくいことが多かったと思います。思っていることを率直に書いている積りですが、大いに反省しています。
新年からは、もっと視野を広げて、いろいろなことをブログに載せていきたいと思います。これからもブログを読んで頂けると嬉しく思います。
ホームぺージについては、新しい業務項目を増やしておりますが、事例のほうが参考になるように思いますので、できるだけ事例を掲載していきますので、こちらのほうもよろしくお願いします。
新年もよろしくお願い申し上げます。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
最近の投稿
- 若手社員の早期戦力化について
- 社員の組織コミットメントについて
- 社員一人ひとりのリーダーシップの必要性について
- 人材育成の取り組みを戦略的に行えていますか
- チームを適切に機能させるタスク管理について
- ビジネスで重要視される目標設定について
- コンフリクトマネジメントについて
- チーム機能を高めるエンパワーメントについて
- 職場リーダーに求められる情況把握力について
- ビジネスパーソンに求められる計画力について
カテゴリー
月別アーカイブ
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)